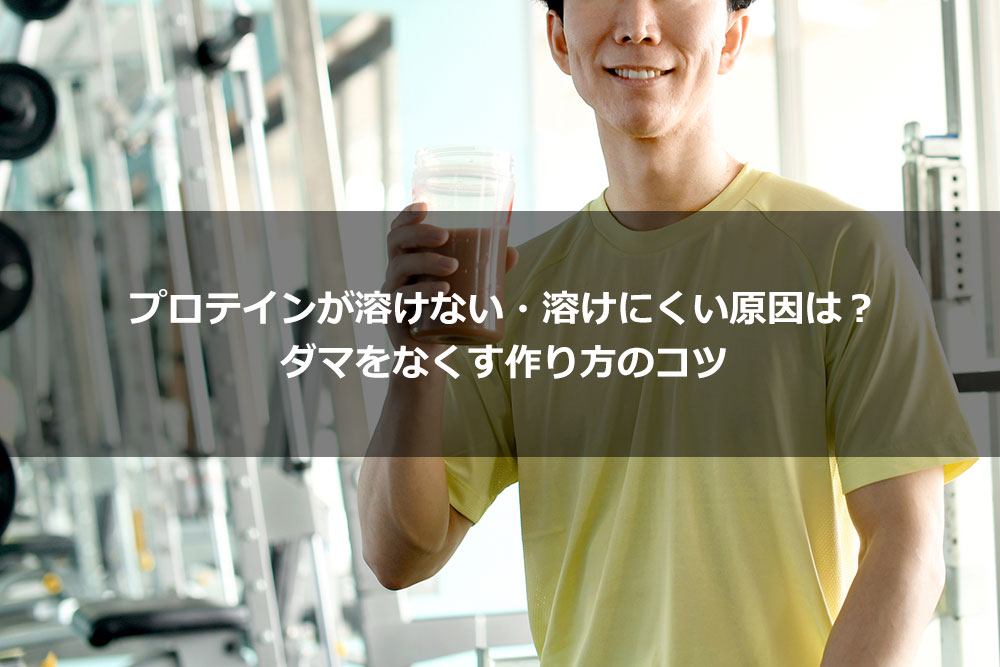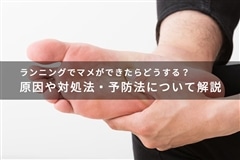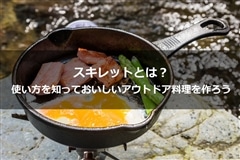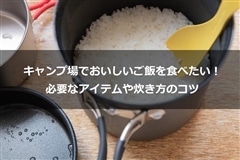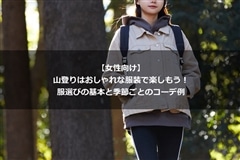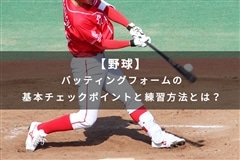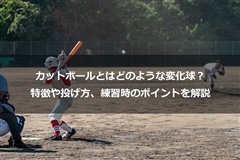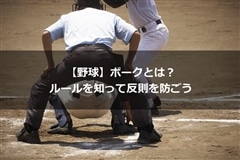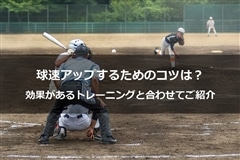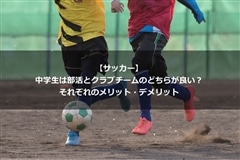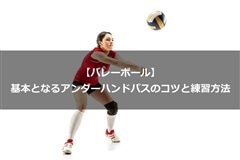プロテインのメリット・デメリットは? 効果を高める活用法

筋トレやスポーツを日課としている人だけでなく、ダイエットやボディメイクなどを目的に使われることも増えているプロテイン。
筋トレやダイエットに役立つものというイメージをお持ちの方は多いでしょうが、具体的に、プロテインを摂取することにはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
ここでは、プロテインのメリットやデメリット、日々の生活に上手に取り入れるためのコツなどをご紹介します。
【目次】
■プロテイン(たんぱく質)の役割は?

筋肉や骨、内臓、髪の毛、皮膚、爪など、人の体はたんぱく質によって作られています。不足すると身体のさまざまな不調につながるとされているたんぱく質は、人が生きていくうえで欠かせない重要な栄養素のひとつです。
日々の食事からも摂取できるたんぱく質ですが、食生活における食事メニューや身体活動のレベルによっては、不足してしまうことも考えられます。日々の生活の中で、不足したたんぱく質を補うための商品が「プロテイン」です。
もともと、プロテイン(Protein)という言葉は「たんぱく質」を意味する英語ですが、日常的には栄養補助食品のことを指して広く使われています。
水や牛乳などに溶かして飲むパウダータイプのほか、ゼリー飲料タイプやドリンクタイプなど、商品によって形状は異なり、自分の好みに応じて取り入れやすいのが特徴です。
たんぱく質を多く配合したチョコレート菓子のような商品も見られます。
■プロテインを飲むメリット

栄養補助食品であるプロテインを活用することで、どのような効果を得られるのでしょうか。日常生活の中にプロテインを取り入れる主なメリットとしては、以下の2点が挙げられます。
・手軽にたんぱく質を補える
1日に必要なたんぱく質の量は性別や年齢、体格、活動量などによって異なるものの、厚生労働省は「日本人の食事摂取基準(2025年版)」において、各年齢や性別ごとに1日の推奨量と目標量を定めています。
例えば、18~39歳の男性の推奨量は65g、女性の推奨量は50gです。目標量は%エネルギーで示され、18~49歳は男女ともに13~20%エネルギー(摂取カロリー全体から見たたんぱく質摂取割合)となっています。※
1日に2,600kcalの摂取が必要な人の場合、たんぱく質の目標量は338~520kcalです。たんぱく質は1gあたり4kcalなので、1日2,600kcalを摂取している人のたんぱく質の目標量は、グラム換算すれば、84.5~130gということになります。
推奨量を基準にして、たんぱく質の必要摂取量を考えたとしても、単純計算で1食あたり20g前後のたんぱく質を摂取しなければいけません。プロテインを活用すれば、1日3食食べるのが難しい日でも、手軽に不足したたんぱく質を補えます。
※出典:厚生労働省 「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html
・脂質を抑えながらたんぱく質を摂れる
肉類や魚介類といったたんぱく質を多く含む食材は、脂質の成分もたくさん含んでいる傾向にあります。たんぱく質は日々の食事から摂取できるとはいえ、ダイエットやボディメイクで脂質の摂取量に気を使っていると、どんな食事内容にすれば良いのか悩んでしまうこともあるでしょう。
プロテインの中には、脂質や糖質といった栄養素を抑えたものがあります。そのようなプロテインを活用すれば、余計な脂質や糖質の摂取を抑えながら、たんぱく質をしっかりと補給することが可能です。
また、ビタミンなどを配合しているプロテインなら、疲労回復効果などを示す生体にとって重要な成分であり、かつ日々の暮らしの中で不足しがちな栄養素を同時に補うこともできます。
■プロテインを飲むデメリットはある?
手軽にたんぱく質を摂取できて便利なプロテインですが、活用する際は注意したいデメリットもいくつか考えられます。
プロテインを飲む時は、以下の点に注意が必要です。
・たんぱく質やエネルギーの過剰摂取になる恐れが
プロテインは、あくまでも日々の生活の中で不足した栄養を補うために活用するものです。食事から十分な量のたんぱく質を摂取できている人がプロテインを飲むと、たんぱく質の過剰摂取になる恐れがあります。
また、たんぱく質にも、一定のカロリーがある点に注意が必要です。過剰に摂取すると余分なたんぱく質が体に蓄えられ、体重増加や肥満につながることも考えられます。
・体に負担をかける可能性も
摂取したものの消費されずに余剰になったたんぱく質は、分解された後に体外へと排出されます。過剰摂取によって、肝臓や腎臓をはじめ、体に負担がかかる可能性がある点にも注意しなければいけません。
また、プロテインの種類によっては、摂取することでお腹が緩くなって、便通異常をきたす可能性もあります。
■プロテインを上手に活用する方法
プロテインは、やみくもに飲んでも意味がありません。しっかりと効果を得るには、上手に活用することが重要です。
プロテインを取り入れる際は、次の2点を意識するのがおすすめです。
・目的に合わせてプロテインの種類を選ぶ
プロテインは、原料や成分の抽出方法からホエイ・カゼイン・ソイといった種類に分けられ、それぞれ特徴が異なります。プロテインを上手に活用するには、目的に合わせてプロテインの種類を選んだり、飲み方を決めたりすることが大切です。
筋トレやダイエット、健康維持など、プロテインを活用する目的が決まっていれば、種類や摂取するタイミングなどを決めやすくなります。
例えば、運動後のたんぱく質補給には、吸収スピードが早いとされるホエイプロテインを活用するのがおすすめです。
一方で、ダイエットや健康維持といった目的でプロテインを取り入れたい方には、吸収スピードが穏やかなカゼインプロテインやソイプロテインが適しています。
飲むシーンや主目的別に、複数のプロテインを使い分けるのも良いでしょう。
・自分に必要なたんぱく質の量を考慮する
1日に必要なたんぱく質の量は、年齢や性別、活動量などによって異なります。
例えば、日頃から運動していて活動量が多い人なら、その分必要なたんぱく質も増えます。一方で、デスクワークでほとんど体を動かさない人は、活動量が多い人と比べて、多くのたんぱく質を摂取する必要がありません。
活動量が多い日や、食事から摂れるたんぱく質が少なかった日はプロテインで不足分を補う、食事だけで十分なたんぱく質を摂取できた場合はプロテインを控えるといった工夫を行いましょう。
また、プロテインはあくまでも足りない栄養を補うための補助食品です。プロテインだけで栄養補給を済ませるのではなく、日々の食事の栄養バランスに気を配り、たんぱく質を摂取することを心がけてください。
■プロテインで不足しがちなたんぱく質を補おう
プロテインは、日々の食事の中で不足したたんぱく質を手軽に補える便利なアイテムです。食事で十分なたんぱく質を摂れない、活動量が多く普段よりもたんぱく質が必要といった状況でも、プロテインがあれば簡便に不足しがちな栄養を補うことができます。
プロテインには、適切に摂取することで多くのメリットがある反面、過剰摂取によるデメリットも考えられるため、利用する際は注意が必要です。
自分自身の生活習慣を考慮して、プロテインを上手に活用してみてください。
RECOMMENDED POSTS
この記事を見た方におすすめの記事