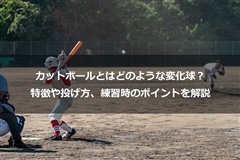【2022年日本サッカー界を総括】日本のサッカーが世界のサッカー界の常識を覆す日が訪れるかもしれない

サッカーの進化は、主にクラブチームによってなされてきた。
W杯は?と思われる方がいるかもしれないが、振り返ってみても、4年に一度開かれるこの大会が、新しい戦術やトレンドを産み出したことはほとんどない。
イタリア・サッカーの代名詞でもあり、サッカーにあまり興味のない層にまで知られている「カテナチオ」にしても、諸説はあるものの、一般的には60年代のインテルが広めたとされている。74年大会で世界に衝撃を与えた「トータル・フットボール」は、そのスタイル、メンバー、監督に至るまで、ほとんどがアヤックスそのものだった。
現代サッカーに目を向けても、「ティキタカ」はバルサ時代のグァルディオラ、「ゲーゲン・プレス」はドルトムント時代のクロップによって脚光を浴びた。10年のスペイン代表や14年のドイツ代表は、自国のクラブが創り出した潮流に乗ることで成功を収めた、ということもできる。
つまり、W杯はトレンドのショウウィンドウではあっても、ファクトリーではなかった。お披露目をする場所であっても、創り出す場所ではなかった。
それだけに、今回のW杯は画期的だった、と言えるかもしれない。
しかも、その立役者は日本である。
日本のプロ野球には、沢村賞という、その年でもっとも活躍した先発完投型投手を対象とした賞がある。ピッチャーにとってはもっとも栄誉ある賞と受け取る人が依然として多い反面、分業化が進んだ現在では、そもそも対象となる先発完投型のピッチャー自体が激減してしまった。選考委員の口からそのことを嘆く言葉が漏れるのも、もはや定番といっていい。
ではなぜ、先発完投型のピッチャーは減ってしまったのだろうか。
かつては、先発のマウンドを任されるのは、そのチームで一番いいピッチャーだった。中継ぎ以降に回されるのは、極論すれば「先発できないピッチャー」たちだった。どれほど先発ピッチャーが疲れても、控えているのが二線級となれば、ベンチは先発を引っ張らざるをえない。
だが、そこに発想の大転換が起きる。
試合を終わらせることを専門とするピッチャー、クローザーを配するという発想である。
野球に限らず、そして日本に限らず、試合がスタートした時点でメンバーに名を連ねている選手がもっとも優れているという考え方は、全世界のスポーツ界に浸透していた。先発するのはレギュラー。できないのは補欠。世界中の誰もが、そんな思いに囚われてきた。
だから、チームでもっとも速いボールを投げるピッチャーを最後に置くという発想は、ある意味、スポーツに於ける常識を根幹から覆すものだった。
クローザーという新たなポジションを産み出した野球界は、続けてセットアッパーというポジションも産み出した。まだまだアマチュア・レベルでは先発こそが一番というイメージは強く残っているが、プロ野球では、先発を人気や年俸で凌駕するセットアッパーやクローザーが珍しくなくなった。
同じことが、今回のW杯を機に、世界のサッカーで起きるかもしれない。
きっかけを作ったのは、森保監督である。
そもそも、サッカーのルールに選手交代という概念はなかった。先発した11人は何があろうと最後まで戦うのが基本であり、運悪く負傷する者が現れたとしても、チームは残ったメンバーで戦うべきだと考えられていた。
だが、フェアプレーに則って作られたイングランド発祥のルールを、曲解して悪用する国が現れた。66年大会に出場したポルトガルは、ブラジルのペレを削って削って削りまくってピッチから叩き出すことに成功した。
勝ったのは、ポルトガルだった。
FIFAが試合中の選手交代を認めるようになったのは、その4年後のメキシコW杯からだった。
それでも、先発メンバーこそが最高だという発想を、多くの国は捨てきれなかった。最高の11人を先発させ、交代はやむを得ない場合のみ、という選手交代がほとんどだった中、この新しいシステムの可能性に気付いた監督もいた。
交代によってやり方を変える、いわゆる「戦術的交代」という発想をW杯に持ち込んだのは、西ドイツのシェーン監督だった。
以来、シェーンの手法は全世界の常識となり、現代に至っている。
ただ、70年大会から94年大会まで、許されていた選手の交代は2人までだった。98年大会からようやく3人の交代が認められるようになったものの、最高のメンバーが先発するという概念自体は、揺らいでいなかった。
だが、今後はわからない。
今大会の森保監督は、三笘を最後まで先発で使わなかった。ジョーカーという形でベンチに置いておき、チームの苦境を打開する切り札として使った。90年大会でカメルーンが38歳のロジェ・ミラを切り札として使った例はあるが、若く、そして多くの人が「日本最高のアタッカー」として認めていた三笘をベンチに置いた森保監督のやり方は、素晴らしく斬新だった。

一方で、三笘は先発で使うべきだという声は、評論家、専門家たちの中からも強く上がっていた。「ネイマールをベンチスタートさせるようなものだ」と怒りを露にする人さえいた。
最高の選手は先発で使うというこれまでの常識からすれば、至極もっともな反応だった。
実際、東京五輪にも出場した三笘は、メキシコのアナウンサーから「まるで日本のネイマールだ!」と絶賛されている。現時点での彼が、すでにネイマールと比較可能な存在なのであれば、ベンチスタートは愚行でしかない。開始直後だろうが終了間際だろうが、ボールを持てば違いを発揮することができるのがネイマールだからである。
ただ、現時点での三笘は、まだネイマールではない。いずれ近づく可能性はあるにせよ、現時点ではまだまだ遠い。いつでも、どんな相手でも、自在に切り裂くことができる、という域には達していない。
ところが、試合途中の投入となれば、話は変わってくる。
先発するということは、100パーセントの状態の相手と対峙するということである。ネイマールならば問題ない。100パーセントの敵と100パーセントのネイマールがぶつかりあえば、勝つのはネイマールだということを誰もが理解している。
では、まだネイマールではない三笘に、ネイマールのような働きをさせるにはどうしたらいいか。森保監督の導き出した結論は、消耗し、70パーセント、60パーセントになった相手に100パーセントの三苫をぶつける、というやり方だった。

実を言えば、森保監督がどこまで考えてこのやり方をとったのかという点については、わたし自身、つかみきれていないところがある。もし70パーセントの相手に100パーセントの切り札をぶつけるという発想が彼の意識の中で明確になっていたのであれば、クロアチア戦で堂安を先発させた理由がわからなくなってしまうからだ。途中投入であればロッベンになれることを証明した堂安だったが、100パーセントのクロアチアにはほとんど何もさせてもらえなかった。
ただ、森保監督の内面はどうであれ、その選手交代が全世界の衝撃を与えたのは間違いない。通常、逆転勝ちというのは実力が拮抗しているか、リードされた側が力で優っていないとなかなか起きるものではないが、今大会における彼と日本代表は、圧倒的な格上を相手に2度も逆転勝ちを演じたのだ。
ベンチに最高の選手を置いておくというやり方は、先発した選手たちに勇気を与えることも世界は知った。三笘が出てくるまでは耐える。三笘が出てくれば流れは変わる。そう信じて戦っているようにしか見えなかった日本を、そんな戦い方でひとまずの結果を残した日本を、世界中のサッカーファン、関係者、専門家が目撃した。
カタールW杯における日本は、ヨーロッパと南米の“支配者”のみが握っていた「人々の胸を打つ権利」を、少しだけ手にすることができた。結果でしか世界を驚かせることのできなかった弱者が、内容で感動させることも可能だと証明もした。
フォロワーは、間違いなく現れる。
そして、その中からまた新しい発想が生まれる。
先発完投を至上主義としていたプロ野球が変わったように、ひょっとするとサッカーにも、ジョーカー的な働きを“本業”とする選手が現れるかもしれない。90分走りきる体力を身につけることをやめ、30分だけ、45分だけプレーすることに特化した選手が出てくるかもしれない。いまはただ背の高い選手を投入するだけでしかないパワープレーを、専門の選手を育て、チームとしてデザインしていくところが出てくるかもしれない。
主にクラブチームによって動いてきた世界のサッカーが、W杯をきっかけに、日本をきっかけにして動き出すかもしれない。
そう考えただけで、鳥肌が立ってくる。
RECOMMENDED POSTS
この記事を見た方におすすめの記事