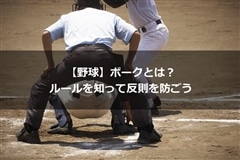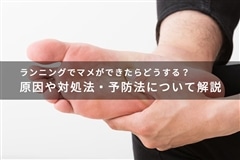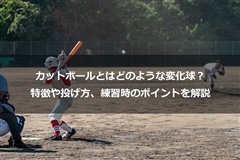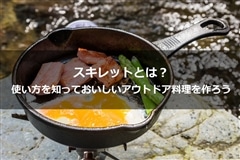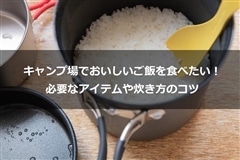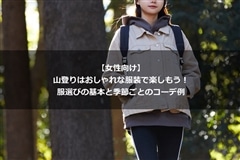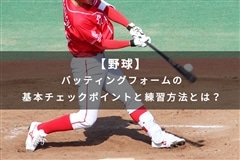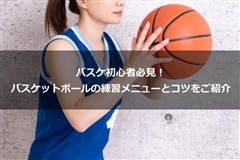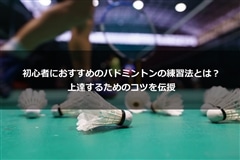5月15日は「Jリーグの日」開幕から33年の「歴史」とさらなる成長への「課題」
 日本代表の森保一監督(右)は、サンフレッチェ広島を指揮して3度のJ1制覇を成し遂げた
日本代表の森保一監督(右)は、サンフレッチェ広島を指揮して3度のJ1制覇を成し遂げた
5月15日は、日本サッカーにとって特別な一日だ。
1993年5月15日に、Jリーグが開幕したからである。
かつての国立競技場で、川淵三郎チェアマン(当時)が開会を宣言してから、25年で33年目のシーズンとなる。積み重ねてきた長い年月は、Jリーグを、日本サッカーを、大きく変えていった。
93年に10チームでスタートしたJリーグはJ1、J2、J3の3つのディビジョンで構成されている。各カテゴリー20ずつで総クラブ数は60にのぼり、40をこえる都道府県にクラブがある。将来的なJリーグ入りを目ざすクラブも列をなしており、発足時に掲げられた「地域密着」の理念が確実に広がっている。
93年の開幕当時の10クラブは、「オリジナル10」と呼ばれる。98年末に横浜マリノスが横浜フリューゲルスを吸収合併して横浜F・マリノスとなったため、現存するクラブは「9」だ。
99年にJ2リーグが発足して以降、オリジナル10のクラブがJ2に降格するケースも出てきた。そのなかで、鹿島アントラーズと横浜F・マリノスの2チームは、一度もJ2に降格していない。
元ブラジル代表ジーコがクラブの哲学を構築した鹿島は、J1リーグ最多となる8度の優勝を誇る。リーグカップでも最多の6回、天皇杯制覇もJリーグ発足後最多の5回を数える。また、2007年から09年にかけて、J1唯一となる3連覇を達成している。近年はタイトルを逃しているものの、Jリーグの盟主と言っていい存在だ。
J1リーグで鹿島に次ぐ優勝5度を数えるのがF・マリノスだ。黎明期にヴェルディ川崎(現在の東京ヴェルディ)と2強を形成し、03年と04年には岡田武史監督のもとで連覇を達成した。
F・マリノスに次ぐのは優勝4回の川崎フロンターレで、サンフレッチェ広島が3回で続く。広島は現日本代表監督の森保一監督のもとで12年と13年に連覇を達成し、15年も頂点に君臨した。
個人記録に目を移すと、遠藤保仁がJ1最多の672試合に出場している。Jリーグ開幕6年目の98年に高卒ルーキーでデビューし、23年まで26シーズンにわたってピッチに立った。J2でも104試合に出場しており、通算では776試合になる。日本代表でも国際Aマッチ最多出場のプレーメーカーは、Jリーグの歴史にその名を強く刻んでいる。
J1通算出場2位は現役の選手だ。浦和レッズのGK西川周作である。38歳の元日本代表は21年目のシーズンを過ごしており、4月20日時点で636試合出場を数える。
3位以下には楢﨑正剛、中澤佑二、阿部勇樹、曽ヶ端準、興梠慎三、小笠原満男、伊東輝悦、山田暢久といった名前が並ぶ。いずれも、Jリーグを彩った選手たちだ。
J1リーグの通算得点ランキングでは、大久保嘉人が191点で首位に立つ。川崎フロンターレ在籍時に3度の得点王に輝き、一気に数字を伸ばした。
2位は興梠だ。鹿島アントラーズ、浦和、北海道コンサドーレ札幌で通算20シーズン稼働し、168得点をマークした。得点王になったことはないものの、12年から20年まで9シーズン連続で2ケタ得点をあげている。
3位以下には歴代の得点王が並ぶ。佐藤寿人、中山雅史、前田遼一、マルキーニョス、小林悠、そしてカズこと三浦知良だ。93年のJリーグ開幕を知るカズは、25年シーズンもJFLのアトレチコ鈴鹿でプレーしている。
ストライカーがランキング上位に並ぶなかで、MF登録の遠藤保仁が103点、藤田俊哉が100点を記録している。遠藤はガンバ大阪を、藤田はジュビロ磐田をJ1優勝へと導いた。キャリアの晩年はともにJ2でもプレーし、プロフェッショナルのスタンダードを後進に伝えた功績も見逃せない。
25年のJ1リーグでは、新たな記録が生まれた。
FC東京の北原槙が、最年少出場記録を更新したのだ。04年3月に森本貴幸が打ち立てた15歳10ヶ月06日の記録を、15歳7ヶ月22日に塗り替えた。リーグカップでも森本を上回り、最年少出場記録を作った。最年少得点記録を更新する可能性もあるが、果たしてどうなるか。

J1リーグ最多出場の遠藤保仁。歴史にその名を刻む
さて、開幕から30年が過ぎ、Jリーグは転換点を迎えている。
これまでは2月または3月開幕で12月閉幕の「春秋制」を採用してきた。3月卒業、4月入学・入社の日本社会のカレンダーに合わせてきたのだが、日本人選手のヨーロッパ移籍の増加により、シーズン中に選手が抜けてしまうケースが増えた。秋春制のヨーロッパ各国とのズレは、外国人選手や外国人指導者の獲得においてもデメリットとなる。
さらには、アジアのクラブナンバー1を決めるチャンピオンズリーグ(ACL)が、23-24シーズンから秋春制へ移行した。ACL最上位のエリートで優勝すれば、アジア代表としてクラブW杯に出場できる。アジアにおけるプレゼンスを高めるためにも、ACLには万全の状態で臨む必要がある。
こうした事情を踏まえて、Jリーグも26-27シーズンから8月開幕、翌年5月閉幕の「秋春制」へ移行することとなった。現行の春秋制は、25年シーズンが最後となる。
Jリーグの持続可能性を考えると、解消したい課題はまだある。
ひとつは「ポストユース選手の強化」である。
高卒やユースから昇格した10代の選手は、所属先で十分な出場機会を得られないケースが目につく。他方、U-20 W杯のアジア予選は、19歳以下の選手に出場資格がある。ポストユース選手の強化の停滞は、日本サッカー界全体の不利益となってしまうのだ。プロ2年目の20歳、3年目の21歳についても同様で、こちらは五輪のアジア予選と本大会で活躍してもらう世代である。
ポストユース選手の強化を目的として、かつてFC東京、ガンバ大阪、セレッソ大阪のU-23チームがJ3に参戦したことがある。そのなかで、若き日の堂安律と谷晃生がガンバ大阪の、久保建英がFC東京のU-23チームで出場機会をつかみ、トップチームでの活躍と海外移籍、あるいは日本代表入りへつなげていったと言われる。

久保建英は15歳でJリーグにデビューし、18歳で海外へ移籍した
Jリーグは日本サッカー協会と協働し、4月にU-22Jリーグ選抜を編成した。元日本代表MF小野伸二らがコーチに入り、関東大学選抜と練習試合を行なった。5月にも選抜チームを編成し、関西学生選抜との練習試合を予定している。
大学生と対戦することにも意義がある。大学生年代の国際大会であるユニバーシアードのサッカー競技が、19年を最後に実施されなくなった。森保一監督の日本代表で常連となっている谷口彰悟、守田英正、旗手怜央、三笘薫、上田綺世らが出場した大会で、大学生の国際経験の機会減は大きな課題となっている。JリーグU-22選抜との練習試合は国際試合ではないものの、緊張感のある機会を増やすことには意義がある。
ふたつ目は「リーグの価値向上」だ。
Jリーグ開幕から2010年代までの海外移籍は、Jリーグのクラブからヨーロッパのクラブへ移籍するという流れが圧倒的多数を占めていた。しかし、ヨーロッパの有力クラブは若い才能の囲い込みに前向きで、国際移籍が認められる18歳の選手に積極的にオファーを出す。日本人選手もその対象となっており、高校卒業とともにヨーロッパのクラブに入団するケースが見られる。
Jリーグのクラブに加入した高卒や大卒の選手も、1、2年で移籍する例が少なくない。注目すべきはその行き先で、オランダやベルギー、オーストリアなどの東欧や、北欧の国々が増えている。
東欧でも北欧でもヨーロッパのサッカーマーケットに入れば、活躍することでステップアップの道は開ける。ただ、サッカーのレベルはどうか。
オランダやベルギーの中位や下位同士でも、Jリーグよりレベルの高い攻防が繰り広げられているのか。必ずしもそうとは言い切れないだろう。
Jリーグの野々村芳和チェアマンは、「Jリーグからイングランド、スペイン、イタリア、ドイツ、フランスといった国のリーグへ移籍できるような道筋を作りたい」と言う。そのためにもリーグのレベルアップは不可欠だ。前述した秋春制への意向にも、「猛暑の時期をできるだけ避けて、試合の強度を高くする、アクチュアルプレイングタイム(APT)を伸ばす」(野々村チェアマン)という狙いがある。
実際のプレー時間を指すAPTは、プレミアリーグと6分ほどの開きがある。ファウルで試合が止まる時間などを減らすことでAPTを伸ばし、高い強度で連続してプレーできるようにする。それによって試合のクオリティを上げ、リーグのレベルアップを促す。その結果として、Jリーグがヨーロッパのトップリーグへつながるとの未来図を描くのだ。
Jリーグ開幕直後はごく限られたものだった海外移籍は、いまやヨーロッパの移籍市場が開く年2回の恒例行事のようなものだ。
挑戦のニュアンスが強い移籍から、選手の価値に見合った移籍へ。開幕から30年以上を経て、Jリーグは新たなフェーズへ突入している。
■Jリーグ 2025 ユニフォーム特集
RECOMMENDED POSTS
この記事を見た方におすすめの記事