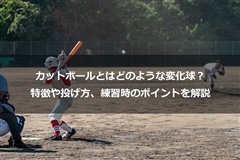『西野朗監督がタイでみせている、カリスマ的な人気は本物なのか』

誰かがこんなことを言っていたとする。
「あいつ、生まれてるよなあ」
二回目の東京オリンピックを迎える年の日本では、意味不明でしかない。人間、存在しているからには生まれている。は? 何を言っているんですか? という感じである。
でも、これが20年後の日本でならば話が違ってくるかもしれない。令和2年の日本人には通じなくても、令和22年の日本人は普通に使っているかもしれない。
なぜって──。
「あいつ、持ってるよなあ」
20年前の日本人は、こんな日本語を使わなかった。持ってる?何を?そう思うのが当たり前。間違っても新聞やテレビといったマスコミが自分たちの媒体を使って公の舞台に登場させる言葉ではなかった。
いまは違う。なぜか勝負強い選手。なぜか大一番で結果を残す選手。そんな選手たちをマスコミは当然のように「持ってる」と評し、受け手も違和感なく理解する。本来は「持ってる」の前につくはずだった「幸運を」とか「強運を」といった単語は省略され、ただ「持ってる」と表現するだけで意味が伝わるようになった。
だとしたら、いまから20年後、幸運とか強運を超えた、そういう星の下に「生まれた」としか思えない選手を表現する際は……なんてことを思った次第。
ご存じの方がいらっしゃるかもしれないが、ブラジルでは昔から「冷たい足」という言い回しがあって、これは才能がありながらも勝ち運のない選手に対して使われてきた。3回のワールドカップに出場し、わずか1敗(86年のフランス戦は引き分け扱いとする)しかしていないのに一度も世界王者になれなかったジーコは、その象徴的存在かもしれない。もっとも、ジーコ御大ご自身は「いや、俺はフラメンゴでならば世界一になっている」と言うかもしれないが。
ともあれ、サッカーの歴史では理屈や理論では解明できない不可思議なことがごまんと起きてきており、これからも、持ってたり生まれてたり冷たかったり、なんだったら「熱い足」なんて言われる存在が現れるかもしれない。
面白いのは、自分自身も含めて、こうした要素を極めて重視し、かつ絶対視してしまっている人間の多さである。持ってる奴は持ち続けているし、持ってない奴はどんなときでも持ってない。そんなふうに思ったりすること、ありません?
でも、冷静に考えてみると、そんなはずはないわけで。
持ってるオトコといえば、まず真っ先に思い浮かぶのはイチロー。じゃ、高校時代の彼は持ってたのか。甲子園で優勝し、ドラフト1位でプロに入ったのか。オリックスに入団してからは、すぐ一軍で活躍できたのか。
サッカーならば本田圭佑か。なるほど、不思議なぐらいワールドカップになると点を取り、本人も「持ってる」という自覚があるようなのだが、ならば、なぜ彼はガンバ大阪のユースではなく石川県の星陵に進まなければならなかったのか。初めて出場した北京オリンピックのあと、手厳しい批判を浴びたときの彼は、「持っている」存在だったのか。
違う、わな。
スポーツの世界に持ってる、持ってないという言葉でしか言い表しようのない存在があるのは事実。ただ、最初から持っていて、最後まで持ち続けた選手など存在しないのもまた事実。逃げ出したくなるような重圧の中で会心の結果を残すことのできた数少ない者のうち、その結果に酔い、自己催眠をかけられたものだけが、持っている存在になれる。
言い方を変えれば、誰だって、どんなに持ってないと言われ、自覚していた選手だって、一瞬にして持ってる存在になれるということ。
いま、タイでは西野朗監督がカリスマ的な人気を誇るようになってきているという。タイの人たちからすると、監督の打つ手一つ、言うこと一つがビンビンに響いてくるらしい。なるほど、わかる。彼らにとっての西野監督は、自分たちが戦ったことのないワールドカップという舞台で、コロンビアやベルギーといった強豪と互角の撃ち合いを演じたチームの指揮官なのだ。アジア人にはできないと思われていたことをやってのけた、いわば「持ってる」指揮官なのだ。
タイ代表選手にとっての西野朗は、ヴィッセルやグランパスの選手にとっての西野監督とはまるで違う。指揮官に心酔した集団と、疑心暗鬼で眺めていた集団では、結果に違いが出てくるのも当たり前。西野監督が特別な星の下に「生まれた」とは思わないけれど、そう思ってくれる選手がいれば、監督という仕事の難易度が大きく下がることは想像できる。
イチローは化けた。本田も化けた。だとすると、これからタイで西野監督が化けたとしても、わたしは驚かない。
RECOMMENDED POSTS
この記事を見た方におすすめの記事