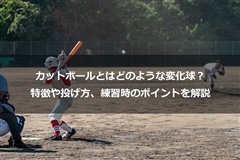【2020年最も印象に残ったアスリート】ディエゴ・マラドーナにあの時、会っていたら“どんな未来”が待っていたのか。

2020年11月にサッカー界、いや世界に衝撃が走る、元アルゼンチン代表のディエゴ・マラドーナの訃報が入った。
マラドーナは1986年のワールドカップメキシコ大会でキャプテンとしてアルゼンチン代表を優勝に導いた。準々決勝のイングランド戦でみせた「神の手ゴール」はあまりにも有名で、引退後は同国代表監督などを歴任した。
自国の偉大な才能が消えれば、どんな国民でも悲しみに暮れる。だが、いまだにマラドーナを神と崇(あが)める人が珍しくないアルゼンチンの人々が受けた衝撃の大きさは、察するに余りある。
わたしにとっても、マラドーナによって運命を大きく左右された存在である。
大学3年生のわたしは、86年のメキシコワールドカップ“アルゼンチンvsイングランド”を現地観戦していた。伝説の5人抜きゴールが人生を変えてくれたのは間違いない。文章を書くという行為の経験も才能もほとんどなかったが、なぜか専門誌の入社試験(作文)をクリアすることができたのは、間違いなく、題材として選んだアステカの記憶、その稀少(きしょう)さによるものだっただろうから。
コロナ禍の影響で、例年に比べれば幾分少なくなったものの、今年もたくさんの方にお話をうかがうことができた。アスリートはもちろんのこと、週刊文春で狂言家の野村萬斎さんやタレントの草なぎ剛(「なぎ」は弓へんに剪)さんのロングインタビューをやらせてもらったのは、貴重な経験になった。
アスリート以外の方をインタビューして感じるのは、インタビュアーに対する向き合い方の違いである。アスリートの場合、取材なんぞ一切受けなくても、あるいは口を開かなくても、結果さえ出していれば大丈夫な部分がある。よって、インタビュアーに対して敵対的であったり、眼中にないといった態度を取るアスリートも皆無ではない。
だが、芸能の世界で生きる人たちにとって、メディアを敵に回すことはファンを失うことに直結しかねない。なので、インタビューの場を大切にする。舞台やテレビでは伝えきれないものを、活字を通じてファンに届けようとする。
これはあくまでも個人的な経験だが、学歴を鼻にかけた若手の女性タレント(約1名)と、立場が約束された古典芸能の中堅役者(これまた約1名)を除くと、取材をしていて不快な気持ちにさせられたことはほとんどない。気難しそうな太田光さんも、矢沢永吉さんも、歌舞伎界の超大物、松本幸四郎(現白鸚)さんも、会ってみれば素晴らしく素敵な方たちだった。これがスポーツになると、感じが悪かった選手のリスト、両手では足りないぐらいに指が折れてしまうのだが(笑)。
ただ、誰にでも胸襟を開いて話をしてくださる方々は、自分にしか引き出せない話を、と目論む欲深いライターからすると、いささか不謹慎かつ傲慢ながら、ちょっとばかり物足りない取材対象でもある。ごく稀に、インタビューをしていて「よっしゃー!」と快哉をあげたくなる時があるが、それはたいてい、口が重くて、なかなか本音を話してくれないアスリートから“ポロッ”と一言がこぼれ出た時なのだ。
もちろん、本音を引き出すためにはそれなりの技術やノウハウもある。で、その大前提としてあるのが「意思の疎通がしっかりとできること」なので、通訳を介さなければならない外国人アスリートの取材には、あまり興味のなかったわたしだった。
18年前も、そうだった。
日韓ワールドカップ開催が間近に迫っていたころ、お世話になっていた出版社から「こういう本の売り込みがきてるんだけど、売れると思う」と相談を受けた。ディエゴ・マラドーナがアルゼンチンで出版した自伝を日本で出さないか、というオファーがあったらしい。
ざっと日本語に訳されたものを見て、わたしは「めちゃくちゃ面白い。絶対に出しましょう」と推した。結局、監修という形でわたしも出版に関わることになり、無事、マラドーナの自伝は日本でも発売されることになった。
忘れられないのは、その後のちょっとした顛末である。
出版社としては何としても本を売りたい。そのためにはプロモーションをやる必要がある。幸い、すったもんだはあったものの、コカイン歴のあるマラドーナの来日も認められることになった。ならば、監修者のカネコタツヒトと、世界のスーパースターを対談させてみようか、という話になったのである。
先にも書いた通り、わたしはネイティブな言語でインタビューができない取材対象にあまり興味はない(話を聞く、ということに関して)。なので、意気込む編集者を前に、わたしは案外、平静だった。できたらすごい。でも、できなくても、「ま、いっか」な感じ。
数日後、暗い顔をした編集者がやってきた。
「カネコさんは会わない方がいいと思います、マラドーナ」
プロモーションの方法を決めるべく、編集者はマラドーナ周辺の人間と打ち合わせをしてきていた。そして、そのあまりのブラックさというか、いかがわしさ、うさん臭さに衝撃を受けて帰って来たのだという。
さもありなん、というのがそのときわたしが感じた率直な印象だった。マイク・タイソンの時も似たような話を聞いた。貧民街を出自とするスーパースターには、必ずといっていいほど、友達面をしてつきまとう輩が数多くいる。マラドーナやタイソンから金をむしることはできないから、代理人、親友を装って仲介料をせしめようとする(本当に親友が代理人をしている場合もあるから、そこがまたややこしい)。
マラドーナの場合は、そこにナポリの反社会勢力もからんでいるという噂もあった。いかがわしくないはずがない。
というわけで、さして惜しいと思うこともなく、編集者からの「会うべきではない」との助言を受け入れた36歳のわたしだった。
プロモーションができなかったことに関係があるのかないのか、マラドーナ自伝の日本版はあまり売れなかった。ただ、聞くところによると、彼の急逝が伝えられてから、1冊1万円を超える値段で取引されたりもしているという。それもこれも、新刊としてあまりに売れなかったがため、あまりにレアだったための現象だろう。
それにしても──。
気心の知れた記者と話す時以外、メディアに対応する際のマラドーナは基本的に猛烈に不機嫌だったという。想像するに、スペイン語もロクにできない日本人のインタビュアーでは、ケンもホロロの扱いを受けたことほぼ確実。
それでも、編集者のアドバイスをぶっちぎり、「それでも会って話がしてみたい」と駄々をこねていたら、いったいどうなったのか。
ちょっぴりそんなことを夢想する、令和2年の暮れだった。