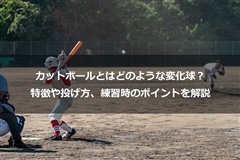サッカー界の異端児、鈴木優磨はストライカーとして日本サッカー界に何を残すのか

仕事はできる。責任感も強い。チームにとって欠かせない人材であることは、誰もが認めている。
ただし、我が強い。
敵に対してはもちろんのこと、目的を達成するためには時に味方に牙を剥くこともある。扱い方を誤ると、チームを崩壊させる雷管になってしまう可能性すらある。
あれはもう20年ほど前のことになるだろうか。82年ブラジル代表のキャプテンだったソクラテスにインタビューした時のことだ。ガチガチに緊張していたわたしは、まずは無難な質問から入るべきだと考え、こう聞いた。
「子供の頃、好きだった選手は誰ですか?」
どんなスーパースターであっても、少年時代の思い出を聞かれれば相好を崩す。経験則から導き出した、自分としては最上の一手のつもりだった質問を、ソクラテスは鼻で笑った。
「サッカー選手に憧れるほど、わたしは愚かではなかったよ」
予想外の反応に激しく狼狽しつつ、しかし、瞬間的に思ったのは「うわ、この人はめんどくさい」ということ。絶句しているわたしを睥睨するように、医学博士の資格を持つ男は付け加えてきた。
「あえて憧れというのであれば、チェ・ゲバラには憧れたな」
こりゃダメだ、と思った。最初に受けた退屈な質問のせいで、彼はこちらを「つまらないやつ」だと認識してしまったらしい。こうなってしまったら、インタビューはまず上手くいかないし、そもそも、どうして取材を受けてくれたのかが不思議になるぐらい、ソクラテスの態度は挑発的だった。これはもう、到底わたしの手に負える相手ではない──心の底からそう思った。
だが、結果的にインタビューは大成功に終わった。1時間が経っても2時間が経っても、それどころか6時間が経ってもソクラテスは席を立とうとせず、ついには「ちょっと待て」と30分ほど中座したかと思うと、「これをプレゼントするから友達にでも配ってくれ」と近所にあった自宅からCDを20枚ほど持ってきてくれた。現役時代に“ドトール(医者)”のニックネームで呼ばれた男は、引退後、“カントール(歌手)”にもなっていたのだ。
なぜ最悪の滑り出しだったインタビューが大団円で終わったのか。理由は簡単、酒の力だった。ドトールはカントールであるだけでなく、誰よりもお酒を愛しているように見えた。素面の彼は気難しく、恐ろしく厭世的だったが、大好きな白ワインを2本、3本と空けていくうち、本来の人好きのする一面が顔を覗かせてきた。別れ際、彼はついに愛妻までインタビューの場所に呼び出し、一緒に手を降って我々を見送ってくれた。

鈴木優磨を見るたび、わたしはソクラテスを思い出す。ピッチで見る彼は常に攻撃的で、敵に対してはもちろん、時に味方に対しても容赦がない。
「我々は確かにイタリアには敗れたが、アルゼンチンには勝った。それだけで、あの大会は満足できる」
「オスカール(日産でもプレーした82年ブラジル代表のCB)が82年のチームはあまりにも攻撃的すぎたから負けたと言っていた?そういうことを言うやつだから、あいつはチームの中で浮いていたんだ。いつでも、どこからでも攻める。それがブラジルだということをわかってない」
こちらがぎょっとするほどにドトールの物言いは直截的だった。ゴールを奪ったあとに相手サポーターを挑発したり、SNS上で森保監督の更迭を求める投稿に「いいね」を押したとされる騒動のあった鈴木優磨には、なぜかソクラテスと似た匂いを感じてしまうわたしである。
あるいは、中田英寿。彼もまた、勝つためであれば軋轢も辞さず、という男だった。
多くの監督にとって、ソクラテスは使いやすい選手ではなかっただろうし、それは中田英寿も同じだった。なかなか鈴木を代表に呼ぼうとしない森保監督に対し、「使いこなす自信がないのだろう」などと揶揄する声もあるが、自己主張の強い選手が敬遠されがちなのは日本、あるいは日本人に限ったことではない。
西ドイツを74年W杯王者に導いたヘルムート・シェーンは、天才肌にしてカリスマだったギュンター・ネッツァーではなく、堅実なヴォルフガンク・オヴェラートに中盤のタクトを委ねた。02年の日本代表監督だったフィリップ・トルシエは、メディアやファンの注目が特定の個人、たとえば中田英寿に集まることを極端に嫌った。彼は中田と自分、どちらがリーダーであるかを周囲に示すべく、偏食の嫌いがあった中田の食にまで注文をつけた。

なので、仮に森保監督が鈴木のキャラクターが原因で代表に呼んでいないのだとしても、それをもって彼を批判するつもりはわたしにはない。まして、トルシエ時代の中田英寿と違い、令和の日本には鈴木と同じ次元の、あるいはもう少し上のストライカーが何人かいる。和を乱すリスクを犯すまでもない、と考えていたとしても不思議ではない。
ちなみに、代表監督時代はありとあらゆるところで軋轢を起こしていたトルシエだが、FC琉球での総監督時代にはほとんどトラブルを起こさなかった。スーパーバイザーとして招聘にも関わっていたわたしは、「丸くなったもんだなあ」と感心しつつ安堵もしたものだが、今から思えば、あれは丸くなったというより、自分を脅かす存在が周囲に皆無だったから、かもしれない。当然のことながらJFLのチームに元日本代表監督を超えるネームバリューを持つ選手はいないし、噛みついてくるメディアもいない。トルシエからすれば、吠えて注目を集める必要もなかったのだろう。
話がそれてしまった。そもそも代表チームというものが選抜チーム、言ってみれば代表監督の好みで作られるチームである以上、よほどのことがない限り、鈴木が森保監督率いるチームに呼ばれる可能性はほぼないと言っていい。ただ、事実かどうかはともかく、アンチ森保の一人と見られていることは、この後、森保監督が職を辞した際には逆に武器にもなる。新監督が森保監督のスタイルを否定する人物だった場合、鈴木のような選手は格好のアイコンだといえるだろう。
一方、鈴木の態度については議論の余地がるのも確かだ。日本サッカー協会の扇谷健司審判委員長は、J1第13節の鹿島―名古屋(5月14日、国立)で鹿島のFW鈴木優磨が得点後に主審をにらみ付けるような行為をしたことについて「非常に大きな問題。レフェリーがしっかり対応しないといけない」と厳しく指摘した。こうした振る舞いは許されるものではない、ストライカーとしてのエゴや攻撃性はありつつも他人への敬意を持った時さらなる大きな成長があるのではないだろうか。
良くも悪くも当たり障りのないところを選びがちな日本社会にあって、敵を作ることを恐れない鈴木優磨のような選手が、わたしは嫌いではない──というか、大好きである。今季、アントラーズには短くはない泥沼の時期があった。勝つことに慣れたアントラーズのファンは怒りを募らせ、時にその矛先は監督や選手にも向けられた。

鈴木は、そこから逃げなかった。監督にすべての責任を委ね、自分は使われているだけという顔を決め込むことができる状況で、あえてサポーターたちの前に立って訴えた。
そして、チームを甦らせた。
こんなことのできる選手が、このまま代表と無縁のまま終わるはずがない、とわたしは思う。あえて重荷を背負い、結果的にさらなる強さを手にしたのだ。もう一花、咲かせてくれないはずはない、と。
RECOMMENDED POSTS
この記事を見た方におすすめの記事