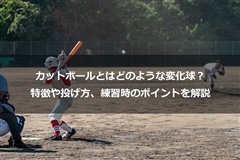遠藤航の挑戦、リバプールの新たなアイコンとしての台頭

フットボールは、イングランドで生まれた。そして、イングランドで生まれたあるフットボーラーが、こんな名言を残した。
「フットボールというのは本当に単純なスポーツだ。22人の選手たちがボールを追いかける。そして、最後にはドイツが勝つ」
発言の主は、33年前のイタリアW杯準決勝で西ドイツに敗れた直後のゲーリー・リネカーだった。21世紀に入ってからのサッカーファンには想像がつかないかもしれないが、このリネカーの言葉、当時のファンには刺さった。強烈に刺さった。最後にはドイツが勝つ。いつもドイツが勝つ。勝てそうもない状況からでも勝つ。そんなイメージが、世界中で共有されていたからだった。
シュツットガルトの中軸として活躍してきた遠藤航のリバプール移籍が決まった。ずっとプレミアでのプレーに憧れていたらしい遠藤にとっては、待望の移籍といえるだろう。ただ、受け入れる側の反応はといえば、ブンデスリーガのデュエル・キングがやってきたことを全面的に歓迎する……というわけではなかった。いや、もちろん歓迎する声もあったのだろうが、そうした声に負けないぐらい「は?」という反応が強かった印象がある。
プレミア・リーグとブンデスリーガ。選手のギャランティやレベルを比較した場合、前者が圧倒的な優位にあるのはいうまでもない。ただ、リネカーの言葉が響いた世代の人間にとって、ドイツは依然として恐るべき存在であり続けている。実際、W杯の実績を比較しても、イングラントとドイツでは正直、勝負にすらならない。
ただ、隆盛を誇るプレミア・リーグしか知らない世代からすると、ブンデスリーガでの実績が「だから、何?」と思えてしまうのも事実だろう。アメリカ人が日本のプロ野球に関心を持たず、日本人が韓国プロ野球をほとんど見ないように、ブンデスリーガを日常的に目にしているイングランドのファンが多くない、という点も関係しているかもしれない。思い出すのは数年前、『韓国のホームラン王を獲得した』というニュースに接した際の、半信半疑だった自分自身の反応である。
もっとも、大外れだったウィリン・ロサリオ(阪神タイガース)とは違い、リバプールでの遠藤は相当にやるとわたしは見ている。どれぐらいやるか。イメージしているのはグラッドバッハからアーセナルに移籍し、今季またブンデスリーガのレバークーゼンに加わったスイス代表のグラニト・ジャカである。年齢を度外視すれば、グラッドバッハ最終年のジャカ(24歳)より、遠藤の方がだいぶ上ではないか、とも思う。
サイズがあり(183センチ)、左利きでもあるジャカは、グラッドバッハ入団当時、エレガントなプレイメイカーとしての役割を期待されていたし、本人もそれを目指していた印象がある。だが、バイエルンやドルトムントほど駒が揃っているわけではないグラッドバッハでは劣勢の試合も多く、崩れそうな中盤を支える仕事が増えていった。
もちろん、低めのポジションから急所をつく一発のロングパスには魅力も威力もあった。ただ、アーセナルが彼に目をつけたのは、そうしたパスセンスというより、高さも含めたディフェンス面ではなかったかとわたしは見ている。実際、当時のグラッドバッハの中盤におけるジャカの守備力は、ずば抜けていた。
ちなみに、ジャカは4シーズン在籍したグラッドバッハで108試合に出場し、6ゴールを記録している。いうまでもなく、これは彼を攻撃的なミッドフィールダーとして見るならば、相当に物足りない数字である。言い方を変えれば、アーセナルが彼を攻撃的な選手とは見ていなかったからこそ、この数字でも声をかけたのではないか、ということにもなる。
一方、遠藤はシュツットガルトに入団した当初から、華麗なパスやドリブルといった攻撃的な役割はほとんど期待されていなかった。チームが彼に求めたのは、いまも昔も変わらぬ守備力。言ってみれば、かつてのブラジル代表におけるドゥンガのような役割だった。
ところが、遠藤は期待された役割をほぼ完璧にこなしたばかりか、期待されていなかったはずの攻撃面でも力を発揮した。2部リーグだった1年目は1得点のみだったが、1部での3シーズンは99試合に出場して12得点と、ジャカのアベレージと総得点を大きく上回っているのである。
アーセナル移籍初年度のジャカは、やってはいけないゾーンでのやってはいけないミスが目立ち、ファンやメディアから手厳しい批判を浴びた。それは、彼自身がプレイメイカーとしての幻影を捨てきれていなかったから、かもしれない。
だが、遠藤に関してその心配はまずない。ベルマーレでも、レッズでも、日本代表でも、遠藤はいつも遠藤だった。誰かを生かす、あるいは生かしてもらうタイプの選手だと、周囲の顔ぶれや相性にプレーが左右されることもあるが、自らも、そして他者からもプレーの第一義を「潰す」ということに置いている、置かれている遠藤の場合、環境に影響される可能性はジャカや、あるいは香川などに比べればかなり低い。
よって、リバプールでの遠藤は大丈夫。シーズンが終わる頃、「は?」とか言っていたリバプールのファンは己の見る目のなさを痛感することになる……というのがわたしの見立て。
ただ、そんなこんなより興味深いというか、ある意味衝撃的なのは、ネットの主役たる世代の、ドイツ・サッカー全般に対するリスペクト、あるいはコンプレックスのなさ、である。
3年前のユーロ決勝トーナメント1回戦でイングランドがドイツを下すと、リネカーはつぶやいた。
「もう“最後にドイツは勝つ”という言葉は終わりにしよう」
あれほどドイツの強さ、しぶとさに苦しめられた世代の象徴が、自らの“名言”を撤回したのである。圧倒的だった時代のドイツを知らない世代が、ドイツを、ブンデスリーガを完全なる格下、あるいは自らを脅かすには足らない存在と捉えるのは、ある意味で当然なのかもしれない。
そして、遠藤はそうした風潮を決定づけた人間の一人でもある。
ご存じの通り、昨年のW杯でドイツは日本に逆転負けを喫した。アジアのチームに逆転負けを喫し、かつ決勝トーナメント進出を逃すようなチームを、どうしてイングランド人が恐れる必要があろう。
というわけで、一部のリバプールのファンが遠藤を軽視するのは、遠藤たちがドイツをやっつけてしまったことも無関係ではない、と見るわたしである。
遠藤からすれば、これはかなり“おいしい状況”かもしれない。高くない期待値は、遠藤のようなタイプ、つまり得点やアシストといった見えやすい仕事を主とするわけではない選手からすると、地位を築いていく上で恰好のポジションだからである。
気付いてみたら、遠藤抜きのリバプールは考えられなくなっていた──そんな近未来の訪れを、わたしは期待し、予想している。
RECOMMENDED POSTS
この記事を見た方におすすめの記事