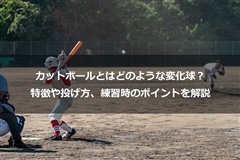逆境からの輝き!香川真司がJリーグで見せる再起の光

人生において訪れる幸運と不運の総量は、比率は、誰しもほぼ同じだという考え方がある。個人的には、いや、明らかに幸運すぎる人、不運すぎる人もいる気がしないでもないのだが、香川真司を見ていると、やっぱりそうなのかな、という側に傾きたくもなる。
彼と、巡り逢ってきた監督を考えてみると、特に。
サッカーは、数あるスポーツの中でも群を抜いて主観的なスポーツである。野球の場合、前年度に数字を残した選手がいきなり干されるということは考えにくい。大谷翔平はどこへ行っても、どの監督にとっても大谷翔平であり、仮に指揮官が極端な主義主張を持っていたとしても、だからといってスタメンから外したりはしない。
だが、サッカーの場合は、前年度は主力としてバリバリに活躍した選手が、監督が変わったことによっていきなり出番を失う、といったことが多々ある。これは、野球というスポーツが基本的には個人事業主の集合体であることに対し、監督の目指す方向性のもと、様々なピースが組み合わさって完成していくのがサッカーだという前提に立つと、より理解していただけると思う。ズラタン・イブラヒモヴィッチをペップ・グアルディオラが使わない、なんてことが起こり得るのがサッカーなのだ。
セレッソ時代、ドルトムント時代の香川は、概ね、監督たちと良好な関係を築いていた。彼が10代のころ、セレッソにはもう一人、柿谷曜一朗という将来を嘱望された若手がいたが、素行の問題などもあり、柿谷がチームから放出される憂き目にあった一方で、香川は常に出場機会に恵まれていた。柿谷がセレッソの育成出身だったこと、年代別のW杯で活躍していたことを考えると、ちょっと驚くべきことである。
10年に移籍したドルトムントでは、ユルゲン・クロップとの出会いがあった。ドイツ国内では知名度を獲得しつつあったとはいえ、世界的にはまだまだ無名のレベルに近かったクロップは、ドイツ語はもちろん、英語も相当におぼつかなかった香川を加入直後から重用した。06年のドイツW杯で日本が惨敗した記憶が、まだ多くのドイツ人に残っていた時代である。いまと違い、日本人であることが限りなくハンデに近かった時代に、自らの可能性を信じ、起用してくれたクロップとの出会いは、間違いなく幸運だった。
しかし、憧れだったというプレミアへの移籍を果たした当たりから、流れは暗転し始める。
彼を引っ張ったスコットランド人の名将、アレックス・ファーガソンの時代はまだ良かった。ドルトムント時代ほどの活躍はできなかったものの、ファンや識者の間では、プレミアのサッカーに慣れていけば状況は好転すると見方が一般的だった。
ただ、勇退したファーガソンのあとを引き継いだデイビッド・モイーズ新監督は、違った考え方を持っていた。
彼は、他の選手にできなくても香川にはできることに注目するのではなく、他の選手はできるのに香川にはできないことを重要視した。求められたのは繊細なテクニックではなく、圧倒的なパワーだった。
ファーガソンが正しく、モイーズが間違っていたというわけではない。エバートン時代のモイーズは、限られた戦力を上手く組み合わせてなかなかに魅力的なサッカーを展開していた。逆に言うと、そうでなければ、チームに対して強い発言力を持つファーガソンが自らの後釜としてモイーズを認めることはなかっただろう。
だが、香川にとっては辛い時代となった。ボールに触ってこそ真価を発揮する彼の頭上を、最終ラインからのボールは無情に飛び越えていく。モイーズが重要視するサイドアタックに飛び込む迫力を、彼は持ち合わせていなかった。
まずは居場所を、次に出番を失っていった香川だったが、初めて指揮を執るビッグクラブの重圧に押しつぶされたのか、モイーズは1シーズン限りでチームを追われる。後任となったのは、バルセロナなどで一時代を築いたオランダ人のファン・ハール。少年時代を『FCみやぎバルセロナ』というチームで過ごした香川にとっては再浮上の好機かとも思われた。

バルセロナの監督時代にシャビやイニエスタを抜擢したことを考えると、ファン・ハールから見た香川は、決して嫌いなタイプではなかったはずである。だが、ヨーロッパ屈指の戦術家としても知られる男にとって、20代半ばとなっていた香川は、自分色に染め上げるには遅すぎる、と判断されたのかもしれない。バルセロナ時代同様、オランダ人選手をチームに引っ張ってきた彼は、香川にチャンスを与えようとはしなかった。
つまり、ドルトムントを離れて以降、幸運は香川に訪れなかった。少なくとも、彼を中心に据えようと考える監督とは、出会えなかった。
一度狂ってしまった歯車は、なかなか元へは戻らない。復帰を決めたドルトムントでは、依然としてクロップが指揮をとっていたが、なぜか、その関係性からは以前の滑らかさは失われていた。
復帰2シーズン目は、プレミアに去ったクロップの後釜に就任したトーマス・トゥヘルから重用されるようになり、第一期に負けないほどの活躍を見せる。チーム自体がいわゆる“ゲーゲンプレス”からポゼッション・サッカーへの回帰を図ったこともあり、香川にとってブンデス時代の最後の“良き時代”と言えるかもしれない。
だが、居心地のいい時間も長くは続かなかった。そのサッカーを評価されたトゥヘルがパリ・サンジェルマンに引き抜かれると、後任の監督たちは香川をチームの軸ではなく、スーパーサブ的な存在として見なすようになった。グラートバッハを立ち直らせたことで知られるルシアン・ファブルは、決してフィジカルに恵まれたとは言えないマルコ・ロイスを中軸に据えたように、テクニックを重んじるタイプの監督だったものの、そのロイスがドルトムントに籍を移していたことも、香川にとっては不安だった。
19年、ローンという形でトルコのベシクタシュに移籍してからは、本人にとっても失意の連続だっただろう。元ドルトムント、元マンチェスター・ユナイテッドということで期待はされたものの、同時に、盛りを過ぎたロートル、という評価もつきまとった。レアル・サラゴサ、テッサロニキ、シントトロイデンと、残念ながらヨーロッパのメイン・ストリームからは遠く離れたチームを渡り歩いた彼は、昨年、再び桜のユニフォームに袖を通すことになった。
だが、ここで数年来のマイナスを一気に取り戻すような出会いが待っていた。セレッソを率いていたのは、彼を宮城から仙台に引っ張ったスカウトでもある小菊昭雄だったのである。
プロとしての経験がない小菊の現役時代を知る人は多くないだろうが、幸運なことに、わたしには高校時代の彼と言葉を交わした経験があった。当時、滝川第二の1年生だった小菊は、黒田監督に挨拶するために宿泊所を訪れた専門誌の記者(わたしのことだ)を質問責めにした。いろいろな学校を取材に回ったが、20代半ばの部外者と積極的にコミュニケーションを取ろうという男子高校生は多くない。正直、プレーヤーとしての印象はほとんどないが、サッカーが好きで好きでたまらない少年、という印象は強く残っている。

巡り合わせの妙もあり、最終的にはJリーグの監督にまで登り詰めることとなった小菊だが、無名のスカウト時代に発掘した香川は、特別な存在だったに違いない。小菊は香川を信じ、信じられたことで、香川は再び輝きを取り戻した。
ヴィッセル神戸に加わったイニエスタは、その知識を、経験を仲間たちに伝えることで、チームと個人の底上げに大きく貢献した。通訳を介すことなく、直接質問をぶつけることのできる香川の存在は、セレッソの若い選手たちにとって大きな財産となるに違いない。
24年シーズン、香川の体調は万全ではない。それでも、信じてくれる監督、温かく迎えてくれたファンの存在は、必ずや彼を復活させるだろう。
もう少し幸運が続いてもいいぐらいの不運を、ここ数年の香川は消化してきたのだから。
RECOMMENDED POSTS
この記事を見た方におすすめの記事