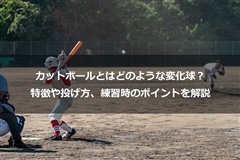長谷部誠、想像を超えたキャリアが放つ眩いオーラ

中国の有名な諺に『男子、三日会わざれば刮目して見よ』というものがある。人は別れて三日もすれば、大いに成長しているもの。次に会う時は目をこすって、つまり注意深くみなければならない、との戒めが込められている。
わたしが初めてこの言葉が本当のことだと痛感したのは、98年1月のことだった。
サッカー日本代表がフランスW杯を目指す戦いを続けていた期間中、わたしは最低でも週に1回のペースで中田英寿と会っていた。彼と川口能活を軸にした単行本を書く予定があったからなのだが、海外サッカーの情報に飢え、かつメディアとの関係が悪化していた中田が、スペインに住んでいた経験のあるわたしとの会話を必要としてくれたから、という面もあった。
「交通費は全部こっちが持つから、毎試合ベルマーレを見て、俺のプレーがどうだったかを聞かせてほしい」と頼まれたのは、彼が代表入りを果たす半年前のこと。以来、わたしはちょっとしたパーソナル・アドバイザー的な気分を楽しませてもらっていた。
代表に選ばれ、瞬く間にチームの中心的な存在へとのし上がっていった中田だが、メディアとの関係がいよいよ悪化していく一方で、わたしとの関係はびっくりするほど変わらなかった。週末は試合会場。平塚での試合だった場合は、彼のポルシェに乗せてもらって東京まで戻る。プライバシーが守られたレストランで食事をし、酔っぱらったわたしがああでもない、こうでもないと講釈を垂れる。いまではちょっと信じられない気もするが、戯言レベルだったわたしの言葉に、中田は熱心に耳を傾けてくれていた。
そんな習慣にピリオドが打たれたのは、いわゆるジョホールバルの奇跡だった。そこから3週間ほど、わたしは新潮社が作家のために用意している執筆用の一軒家に軟禁され、元ミス東京だったという優しい編集者に尻を叩かれまくった。いまから思えば、少しでもW杯初出場の熱が残っているうちに、という彼女の熱意は至極もっともなのだが、基本的には雑誌の物書きで、書き下ろしの単行本に取り組んだ経験のなかった当時のわたしにとっては、遠洋漁業のマグロ船に押し込まれたような気分だった。
書き上げるまでにかかったのは、確か、1カ月少しだった記憶がある。12月中旬には、中田が選ばれた世界選抜の試合に同行するために、一緒にマルセイユまで行った。単行本にはその様子も書かれているので、おそらく、年をまたいでの1カ月だったのだろう。苦行を終えてようやく監禁部屋から解放されると、いつの間にかわたしの担当編集者とも親しくなっていた中田から「本、書き終わったんでしょ。メシ行こうよ」との誘いが入った。
指定された待ち合わせ場所は、四ツ谷の居酒屋だか寿司屋だったか。何事にもルーズなわたしがちょっと遅れ目で店に入っていくと、時間に几帳面な中田はすでに席についていた。そこまでは、いつもと同じ。ただ、彼の回りには、見慣れない人たちが座っていた。
作家の村上龍さんと、幻冬舎社長の見城徹さんだった。
度肝を抜かれた、なんてもんじゃなかった。こちとら、たった1冊単行本を出しただけの、かつもう二度と出すつもりもニーズもないであろう一介のライター。かたや直木賞作家で、かたや業界の風雲児。あたふたするだけのわたしを尻目に、中田はいつものように会話と食事を楽しんでいた。
そのときに思ったのだ。これが、男子三日会わざれば、というヤツだな、と。
ジョホールバルを終えてからの数週間で、中田英寿の交遊関係は飛躍的に広がっていた。ありとあらゆる日本の名士が彼との会食を希望し、好奇心旺盛な中田は、興味のある人からの誘いには積極的に応じていたらしい。成功者と出会い、会話を交わすことで、その人が放っていたオーラの残り香が沈着する。それを積み重ねて、積み重ねていくうち、いつしか自分自身もオーラを放つようになっていく。たった1カ月で、中田はこちらを怯ませるほどの存在に変貌していた。
同じような経験は、本田圭佑にも体験させてもらった。
初めて彼をインタビューしたのは、09年の夏、北京五輪から1年がたち、オランダ2部リーグのシーズンが終わった直後だった。「負けん気は強いけれど、同じ年のころの中田英寿ほどの自信はないな」というのが、率直な感想だった。こちらが緊張することはまったくなかったし、本田からは取材される喜び、のようなものがはっきりと感じられた。有体に言えば、すごく楽しく、そして気楽にできたインタビューだった。
9年後、某企業の広報から思いがけない依頼が舞い込んできた。本田圭佑と契約し、大々的にCMを作ることになった。ついては、そのインタビュアーを引き受けてもらえないだろうか、というオファーだった。本田圭佑本人からのご指名だという。
撮影場所は、横浜市内の小学校だった。一足先に現場に入り、のんびりと読みかけの単行本に目を通していると、数十人いたスタッフに緊張が走るのがわかった。本田圭佑の登場だった。
久しぶり──と手を差し出しながら目を見た瞬間、衝撃が走った。そこにいたのは、9年前の本田圭佑とは完全な別人だった。いや、変わっていない部分もあるのだろうが、にじみ出るオーラが、自信が、9年前とは比較にならないレベルになっていた。
すっかり狼狽したわたしは、完全にインタビューのリズムを見失ってしまった。なんとかCMは無事放映されたものの、以来、本田からインタビュアーとしての指名が入ったことはない。
もっとも、わたしが人生においてもっとも刮目させられたサッカー選手は誰かと問われれば、答は決まっている。中田でも本田でもない。長谷部誠である。
中田は、U17日本代表で、韮崎高校を卒業する際にはすべてのJリーグ・チームが獲得に動いた逸材だった。本田は、わたしが信頼するスカウトの方から「ひょっとすると小倉(隆史)よりいいかもしれないから注目しといて」と言われたこともあって、星稜高校の試合を観に行ったことがあった。後の知名度とは比べ物にならないにせよ、彼らは、高校時代からある程度名前の知られた存在ではあった。
藤枝東の長谷部という選手は、恥ずかしながら見たことも聞いたこともなかった。
当時の日本サッカー界の常識というか感覚では、日本代表の中核になるような選手は、高校時代からある程度脚光を浴びた存在、という認識があった。長谷部は違った。浦和レッズへの入団が決まった際、彼の決断がニュースになった記憶はないし、プロとしてのデビューに注目が集まったこともなかった。
もちろん、後に日本代表の監督となる森保一のように、まったくの無名校(長崎日大)から社会人(マツダ)に入り、そこから日本代表になる──といった例もなかったわけではない。日本代表のキャプテンとなった柱谷哲二、井原正巳といった選手たちも、頭角を現したのは大学に入ってからだったし、彼らは基本的に守備の選手だった。

まさか、長谷部が日本代表のキャプテンとなり、ブンデスリーガ制覇を経験し、ドイツでも伝説的な存在と呼ばれることになろうとは、まったくもって、夢にも思わなかった。
実は、11年に出版され、スポーツ選手の著書として史上初のミリオンセラーを記録することになった『心を整える』は、木崎伸也というわたしの後輩ライターが執筆を担当しており、その彼から長谷部についてのいろいろなエピソードを聞かせてもらう機会は多かった。個人的な面識はほぼなかったが、こちらとしては勝手に親近感を抱いていた。
しかも、朝日新聞だったか読売新聞だったか、「あなたにとって忘れられない一冊は?」という書評ページのインタビューで、長谷部は『決戦前夜』と答えてくれていた。わたしが中田英寿と川口能活に密着し、新潮社近くの一軒家で缶詰になって書き上げたあの一冊である。
そんなわけで、F1イタリアGPの取材を終え、フランクフルト経由で帰国しようとしていたわたしは、すぐ近くの席に長谷部が座っているのを見つけると、すっかりうれしくなってしまった。
とはいえ、明らかに休息モードに入っているプロ・アスリートに機内で声をかけるのも気が引ける。成田に到着し、彼が席を立ったタイミングで声をかけ、振り返った彼と目があった瞬間……またまた息を呑んだ。
オーラ、ビッカビカでした。
イタリアでフェルナンド・アロンソやジェンソン・バトン、佐藤琢磨といったF1界のスターに話を聞いた時には何も感じなかった人間が、長谷部のオーラにはほとんど弾き飛ばされそうになってしまった。
「あ、あの、ライターのカネコと申しますが……」
「ああ、木崎さんからお名前はうかがってます」
優雅に頭を下げられてしまうと、もうわたしの口から次の言葉は出てこなかった。情けないにもほどがあるが、残念ながら、それが事実だった。

あれからさらに10年以上に月日が流れた。活躍の舞台をフランクフルトに移し、ヨーロッパ・タイトルを獲得した長谷部は、掛け値なしに、ドイツ人からも惜しまれて現役を終えた。
40歳の彼は、どんなオーラを放っているのだろう。興味もあり、怖いようでもあり、わたしの気持ちは、いろいろと複雑である。
RECOMMENDED POSTS
この記事を見た方におすすめの記事