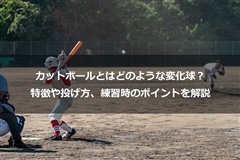Jリーグ30周年のMVPに、遠藤保仁が選出。その背景にあった“時間軸を操る力”とは

サッカーメディアなどによって選出されるJリーグ30周年のMVPに、遠藤保仁が選ばれた。
選考委員会を構成するメディアの中には、『サッカーマガジン』と『サッカーダイジェスト』が名前を連ねていた。かつてダイジェストに所属し、両誌の因縁やライバル意識を知る者の一人としては、なかなかに感慨深いものがあるが、いずれにせよ、彼らが選んだMVPの名前に異論はない。日本サッカー30年のMVPではなく、Jリーグ30年の歴史におけるMVPとなれば、Jリーグ一筋でいまもキャリアを続けている遠藤を他においてない。
ただ、彼が横浜フリューゲルスに入団した当時を思えば、ちょっと信じられない気もする。
ご存じの通り、遠藤は「黄金世代」と呼ばれた99年ワールドユース組の一人である。鹿児島実時代も、それなりの注目は集めてもいた。
とはいえ、この世代はあまりにも豊作だった。一個上に中村俊輔がいて、同年代では稲本潤一がいて、何より、小野伸二がいた。いかに遠藤の才能が豊かだったとしても、世間の注目は浦和レッズ入団1年目に即レギュラーになったどころか、いきなりフランスW杯のメンバー入りを果たしてしまった小野伸二ばかりに注がれた。
実際のところ、単純な才能の比較であれば、小野を凌駕する存在は同世代はもちろん、Jリーグ30年の歴史に置いてもいまだ出現していない、と個人的には思う。あのケガさえなければ──。シドニー五輪のアジア予選で無意味かつ凶悪なライダーキックを見舞ったあの選手は、日本だけでなく、世界のサッカーに大損失を与えてくれた。思い出すたび、腸が煮えくり返る。
だが、遠藤の才能が小野より大きく劣っていた、というわけではない。まったく、ない。両足を自在に扱い、ひょっとしたらジダンより上手いのでは、と思わせるほど柔らかなトラップをする小野ほどではないものの、遠藤の膝も、異様なレベルで軟体動物的だった。バンッ、とか、バシッという擬音で表現されるプレーも、遠藤の足にかかると「ネチョッ」という音が聞こえてきそうだった。それぐらい、ボールを止める技術は変態的だった。
そして何より、彼には小野でさえもっていない異能があった。
時間軸を操る力である。
昔のマンガで、『サイボーグ009』という作品をご存じの方はいらっしゃるだろうか。石ノ森章太郎さんの手になる、悪の組織と戦うサイボーグたちの物語である。9人のサイボーグたちは、文字通り常人離れした能力を与えられており、アメリカ出身の002ことジェット・リンク、日本出身の009こと島村ジョーには、知覚、思考、運動速度を加速させる『加速装置』というシムテムが組み込まれていた。端的に言えば、敵よりも速く感じ、速く考え、速く動くことができる能力である。
残念ながら、遠藤には相手より速く走る能力は与えられていなかった。当時の日本サッカー界には、九州出身の選手には技術ではなくパワーやスピードを求めがちな傾向があり、だからなのか、フリューゲルスに彼を迎えた先輩たちからは、あまり芳しくない評判を聞いた記憶がある。
曰く「アニキ(長男の拓哉、次男の彰弘)に比べるとスピードがない」、曰く「上手いんだけど特徴がない」、曰く「鹿児島実出身なのにフィジカルが強くない」エトセトラ、エトセトラ。
だが、監督の見方は違った。スペイン代表、バルセロナで活躍し,引退後はヨハン・クライフの右腕として知られたカルロス・レシャックは、およそ九州出身者らしからぬ、ゆったりとしたテクニシャンにどんどんと出場機会を与えた。というより、レシャックでなければ、遠藤保仁がJリーグの舞台に立つ機会はもう少し遅れていたかもしれない。走るな、考えろというのがレシャックの心情だったからである。当時、フリューゲルスの選手だった永井秀樹(現ヴィッセル神戸GM)は、強烈に覚えているレシャックの言葉がある。
「お前は走りながら方程式が解けるのか? 解けるならいい。ただ、解けないのであれば、走るな」
サッカーがチェスにたとえられることもある競技だということは、もちろん永井も知っていた。ただ、彼が育ってきた環境は、考えることと同じぐらい、いや、場合によってはそれ以上に走ることも重要視されていた。技術の足りない選手は、技術を磨くことを要求されるより、走力やパワーで補うことを求められていた時代であり、技術の優れた選手であっても、走れなければ否定的な評価を下されることも珍しくなかった。
だが、レシャックはまず考えることを優先させ、考えのない走りを完全に否定した。
クライフの右腕として知られたレシャックは、必ずしも日本で成功したとは言い難い監督だった。ただ、いまになって思えば、彼の来日は遠藤と出会い、見出すためだったのではないか、という気さえしてくる。
決して駿足ではない遠藤には、009に比べればずいぶんと限定的ではあるものの、サッカーという競技においては極めて有効な加速装置が内蔵されていた。普通の選手が1秒間の間に下すことのできる判断、起こすことのできる行動が1か2だとしたら、彼は3から4のことを考え、こなすことができた。
その象徴とも言えるプレーが、世界的にも有名になった“コロコロPK”だった。
相手GKの動きをギリギリまで見極め、どちらに動くか、あるいは動かないかを確認した上で、絶対に枠を外さないサイドキックでコロコロと逆をつく。失敗する可能性が10パーセントから20パーセントとされるペナルティキックにあって、遠藤のスタイルほど確実性を高める方法はない。
だが、世界クラブ選手権で日本人のみならず、数万人、数十万人、あるいはもっと多くの世界の人々が知ることになった“コロコロPK”には、わたしの知る限り、世界のどこからもフォロワーは現れなかった。あれほど有効で、あれほど簡単に見えるやり方を、世界の誰も真似しようとはしなかった。
当然である。
キッカーが動き出さなければ、GKまた動かない。つまり、GKが動き出すということは、蹴る側も動き出していることになり、ボールに向かう助走は、蹴るために振り上げた足は、どこかの段階でルビコン川を超える。つまり、引き返せない一線を超える。超えてしまえば、そこから働くのはキッカーの意志ではなく、単なる惰性、慣性の法則である。GKがとてつもなく早く動いてでもくれない限り、キッカーはどこかの時点で、キックの成否を運否天賦に任せるしかない状況に突入する。もちろん、そのことを一番よく知っているのはGKであり、ゆえに彼らは、ぎりぎりまで自分が動く方向を偽装しようとする。
ところが、通常の選手であればルビコン川を超えてしまったはずの時点で、まだ意志の力を働かせる余裕を残していたのが遠藤だった。彼の時間軸は、他の選手たちとは明らかに違っていた。それこそが“コロコロPK”の秘密であり、だからこそ、体内に加速装置的な機能を持たない選手には真似をすることができなかったのだ。
振り上げた足がボールを捉えるか捉えないかというところですら意志の力を介入させることのできる遠藤にとって、360度に動く自由が補償され、かつ、蹴らないという選択肢も含まれるフィールドでのプレーは、さながら、止まっているパイロンの間をすり抜けていく感覚に近かったのかもしれない。そうとでも考えなければ、スピードやパワー、サイズがあるわけでも彼が、四方を敵に囲まれた中盤の底というポジションで輝き続けた理由が、わたしには説明できない。
43歳になった遠藤は、さすがにフルタイムを戦うのが難しくはなっている。ただ、彼が持つ最大の武器は、依然輝きを失ってはいない。老獪な009には、もうしばらく日本のファンを楽しませてほしいと思っている。
RECOMMENDED POSTS
この記事を見た方におすすめの記事