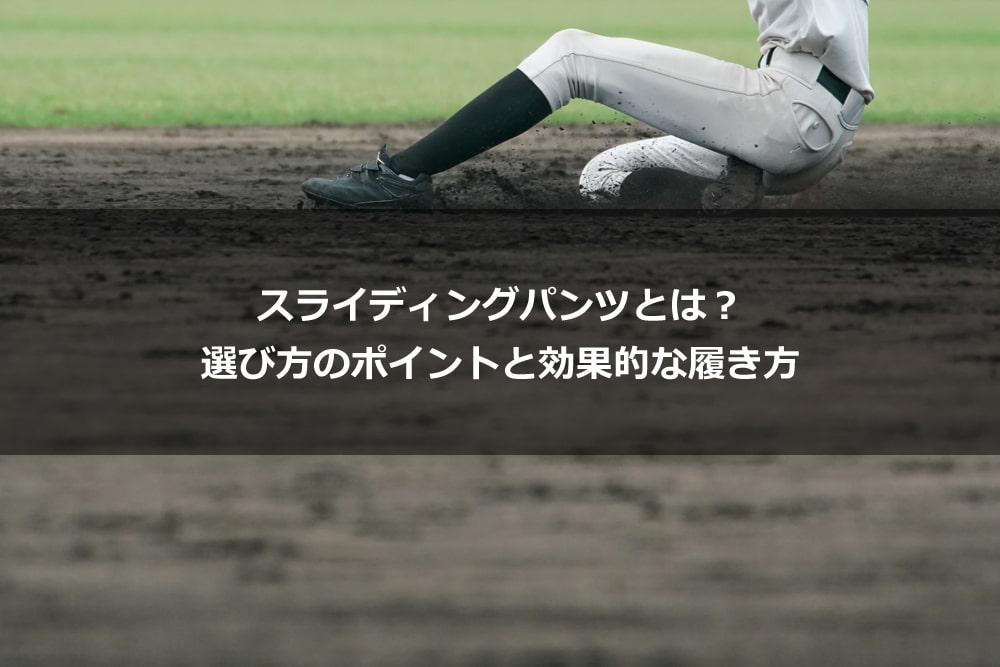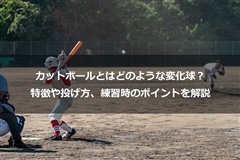メジャーリーグで輝く吉田正尚、その原動力は大谷翔平の言葉か

その場で聞いた選手は魂が震える思いだっただろうが、映像で見たわたしも脳天を稲妻で貫かれたような気分だった。すげえ、なんてもんじゃない。もう完全にノックアウト。
やっぱ凄いわ、大谷翔平。
「ぼくから一個だけ。憧れるのをやめましょう。ファーストにゴールドシュミットがいたりとか、センターみたらマイク・トラウトがいるし、外野にムーキー・ベッツがいたりとか、野球やってたら誰しも聞いたことがある選手がいると思うが、やっぱり憧れてしまっては超えられない。ぼくらは超えるために、トップになるために来たので、今日一日だけは憧れを捨てて、勝つことだけを考えていきましょう。さあ行こう!」
もちろん、痺れたりノックアウトされたりしたのはわたしだけではないはず。視聴率から勘案するに、数千万人単位の日本人が強烈な感銘を受けたに違いないとは思う。憧れを捨てる。今日一日だけは捨てる。言えることじゃない。そもそも、これから決戦に臨もうとする一選手が、急に思いつくような発想でもない。
きっと、彼はずっと考えていたし、狙っていたのだ。仲間たちにそう伝えるタイミングを。
唐突に思い出したのは、98年のフランスW杯だった。
もはやリアル・タイムでは体験していない、という方もたくさんいらっしゃるだろう。日本にとって初めて出場したW杯本大会。初戦の相手はアルゼンチン。マラドーナは引退したものの、トップにはバティストゥータがいて、中盤では“チョロ”の愛称を持つシメオネが睨みを効かせていた。ほぼすべての選手が、ヨーロッパで活躍するトップスター。正直、わたしは日本が勝てるなどとは1ミリも思っていなかったし、それは、実際に戦う選手たちのほとんどがそうだっただろう。
案の定というべきか、結果は0-1に終わった。スコアの上ではまずまずの善戦だったが、日本のチャンスをほぼ皆無で、勝つチャンスはもちろん、引き分ける可能性もほぼゼロという試合内容だった。
試合後、わたしはアルゼンチンのパサレラ監督のもとに向かった。岡田監督や日本選手のもとには日本の記者団が殺到している。そこで誰もが聞ける話を拾うより、スペイン語が理解できる人間しか聞けないパサレラ監督の話を聞く方がバリューがあると考えたからだった──というのはあとづけの理由で、本当のところは78年W杯の英雄でもあるパサレラが、大会得点王になったケンペスと同じぐらい好きだったからではないか、といまになって思う。
とにかく、勇んで向かったアルゼンチンのチーム関係者が通るミックスゾーンに、憧れのパサレラは渋い表情で現れ、わたしは拙いスペイン語で問いかけた。
「日本チームについてどう思いましたか?」
そこで、言われてしまったのだ。
「彼らは我々を尊敬しすぎているようだったね」
打ちのめされた。パサレラのいう「彼ら」とは、もちろん日本チームのことなのだろうが、そこには間違いなく、わたし自身も含まれていた。
わたしは、アルゼンチンを尊敬しすぎていた。どうやったら勝てるかを真剣に考えるより、どうやったら恥をかかないか心配する方に重心は傾いていた。それも、めちゃくちゃ大きく傾いていた。
そんなふうに考える国民のいる国が、世界王者になることしか眼中がないチームに勝てるはずがなかった。どちらが勝つかわからないからスポーツは面白い。だとしたら、端から勝てるはずがないと踏んでいた日本の試合が第三者にとってスリリングだったはずはないし、初戦に勝利を収めたにも関わらず、パサレラの表情が苦り切って見えたのは、きっと、試合自体が恐ろしく低調だったからなのだろう。
長いこと、本当に長いこと、わたしにとってのこのアルゼンチン戦は、苦い思い出であり続けてきた。そこに飛び込んできた、大谷の言葉だった。
98年当時、アルゼンチンと日本の間には決して小さくはない力の差があった。それは間違いない。ただ、もし試合前のロッカールームで、大谷のような言葉を発する者が一人でもいたらどうだっただろう。
というより、もし日本サッカーがW杯の決勝に進出する日がきて、相手がブラジルだとしたら、そこでも大谷の言葉は必要なのではないだろうか。つまり、彼の言葉は過去に「たられば」で当てはめるより、いつか来るであろう、あるいはきてほしい未来のためにも宝物として記憶しておくべきなのではないだろうか。
そもそも、なぜ大谷はあんなことが言えたのだろうか。
彼自身が、常に戒めとして自分に言い聞かせているから、ではなかったか。
野球の母国に対する尊敬と、そこでプレーする選手たちに対する憧れは、きっと大谷自身の中にもある。それでも、自分が結果を出すためには、過度の憧れや尊敬は毒にもなりかねない。ゆえに1試合ごとに、1打席ごとに、1球ごとに、彼は昔から抱いてきた大切な思いをそっと棚に上げる作業を繰り返してきたからではないだろうか。だからこそ、普段はそういう作業をしていない日本のチームメイトのために、最終決戦を前に、自らを律してきた教訓を語ったのではないか。
そんな気がした。
アメリカに渡る日本の野球選手、ヨーロッパに移籍する日本のサッカー選手。きっとみんな、野心と同じぐらい強い憧れがある。大谷は、そんな気持ちを全面的に否定するのではなく、ほんの一瞬だけしまっておくことの大切さを説いた。
その金言が、吉田正尚を救ったかもしれない。
侍ジャパンでの吉田は、大谷に負けないぐらいの存在感を放つ大黒柱の一人だった。だが、所属チームでの彼は、海のものとも山のものともしれないルーキーでしかない。
憧れは、時に自分を蝕むことがある。
憧れが過ぎれば、日本ほどには結果が出ないメジャーでの成績を、レベルの差に求めてしまうかもしれない。長打が出なければ、外国人に比べれば小さい自分の肉体に求めてしまうかもしれない。
しかも、器用さは十分に認められた日本のバッターも、長打に関しては高い評価を勝ち取っているとは言い難い。日本屈指の大砲だった松井秀樹もアメリカでは中距離打者と見なされ、同じく長打を期待された筒香嘉智も依然として結果を残せずにいる。
だが、ここまでのところ、吉田は日本での吉田と同じように長距離砲であり続けている。途中、決して短くはない不調の時期があったにも関わらず、口うるさいことで有名なボストンのメディアも吉田の可能性に疑念をはさむことなく、また、吉田自身も何事もなかったかのように不調を脱出し、逆に安打を重ねたりもしている。
野球は、どれほど偉大な選手であっても好不調の並にさらされるスポーツでもある。そして、日本では「いつか抜けるさ」と思えたスランプの日々を、「俺では無理なのかな」と考えさせてしまうのが憧れや尊敬の毒である。
この原稿を書いている5月18日現在、本塁打6本、打率3割を記録している吉田は、いまのところ、過去の日本人長距離バッターを苦しめた毒とは無縁のように見える。
もちろん、それは彼自身の努力や才能なくしてなりたつものではない。そのことを十分に思いつつ、稲妻に打たれたわたしは、あの言葉が吉田の力にもなっているように思えて仕方がないのだ。
RECOMMENDED POSTS
この記事を見た方におすすめの記事