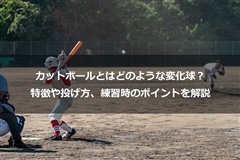【2024年の日本サッカー界を総括】日本人指導者に見えた新たな可能性

ヴィッセル神戸の2連覇で、24年のJリーグは終わった。以前であれば、元日の天皇杯をもってシーズン終了というのが日本サッカー界のカレンダーだったが、最近では物足りなさを覚えることもなくなってきた。何事も慣れ、ということなのだろう。
さて、日本サッカー界にとって今年はどんな1年だったか。高知のファンにとっては初のJ昇格を決めた忘れ得ぬ年、ということになるだろうし、逆に岩手のファンからすれば、JFLに転落した悪夢の年かもしれない。それぞれの地域、贔屓のチームによって受け止め方はそれぞれだろうが、個人的には、あとになって振り返ってみれば「日本人指導者の可能性にスポットライトが当たった年」になるのでは、と思っている。
Jリーグ誕生以来、多くの日本人選手が海外に渡り、もはやヨーロッパのクラブと契約する、出場する、いや、ゴールを決めるぐらいではニュースにすらならない時代となった。長く日本人の胸深くに巣くっていた欧米への劣等感は劇的なまでに取り払われ、本気で日本サッカーはW杯で優勝できると考えるファンも増えてきた。

いまから50年前、74年のW杯で世界の頂点に立ちかけたオランダが、未だ黄金のカップを掲げられていないことを思えば、「頂点が見えてきた」と「頂点に立つ」との間には途方もないほどの違いがある。もしかすると、ここからが日本サッカーにとっては長く険しい旅路の始まりか、と思わないこともないが、何にせよ、自分たちのサッカーと可能性に自信を持つのは悪いことではない。
ただ、選手たちの能力に対する不安やコンプレックスが消えていったことで、長く日本のサッカーファンが持ち続けていた“自虐的なエネルギー”は行き場を失った。以前であれば、W杯で負けるたびに「だから所詮日本人は」とか「やっぱり欧米には歯が立たない」といった反応が巷に溢れたものだが、プレミアやブンデス、リーガの有力選手を多数擁するとなるとそうもいかない。新たなターゲットを求めるエネルギー保存の法則が行き着いたのは、日本人指導者、端的に言ってしまえば森保監督だった。
選手は海外に渡った。ビッグクラブで活躍するようにもなった。一方、指導者が海外進出した例は、選手とは比べ物にならないほどに少ない。数少ない例にしても、日本サッカー協会を後ろ楯にしたアジア諸国での派遣であり、呼ぶ側が身銭を切ったケースはほとんどない。急速に高まりつつあった日本人選手の評価に比べ、指導者たちが置いて行かれた形に映りがちだったのは事実である。

実は、森保監督に対する凄まじい逆風が吹いていたカタールW杯以前の段階でも、彼は日本代表の監督として歴代最高の勝率を記録していた。そんな指揮官に対し、ファンはもちろんのこと、メディアの中からも「無能」と断ずる声まで出ていた。サッカーがつまらない、でもなく、成績がひどすぎる、でもなく、「無能」である。
カタールでドイツ、スペインを破ったことで一度は消えたように見えた森保監督に対する逆風は、今年の頭、アジアカップで優勝を逃したことで勢いを取り戻した。駒はあるのに、監督が無能だから勝てない──そんな声が再び多数派になろうとしていた。
ところが、不安視する声もある中で始まったW杯のアジア最終予選で、日本代表は圧倒的な強さを見せた。
森保監督を無能と決めつけていた人たちにとって厄介だったのは、森保監督を絶賛する声が対戦した国々や、第三者であるヨーロッパや南米からも上がったことだった。日本人監督だからダメ、という論理が、日本人以外から否定されてしまったのだ。知名度でも実績でも報酬でも森保監督とはケタが違ったマンチーニ監督率いるサウジアラビアですら、日本にほぼ手も足も出なかったのだから、欧米メディアやファンの驚きもわからないではない。

個人的には、アジアカップであれほど不安定だった日本が、最終予選で見違えるような姿を見せた最大の要因は、GK鈴木の成長にあると思っている。端的に言えば、弱点だったポジションが弱点ではなくなり、途中からはむしろストロング・ポイントとなった。マイナスがゼロへ、さらにはプラスに転じたわけだ。そして、なぜそうなったかと言えば、「鈴木を外せ」の大合唱の中、森保監督が起用にこだわり続けたからだった。賭けてもいいが、もしあの段階で森保監督が周囲の声に屈していれば、鈴木はまったく違う道を歩んでいた。
ただ、逆に言えば、森保監督の能力が劇的に高まった、というよりは、蒔いておいた種が実を結んだ1年だった、ということもできる。それでいながら、あれほど激しかった森保監督に対する逆風が、ほぼ完全に消えてしまったところに、サッカーを論じる日本人の底の浅さを──自戒も込めて──痛感させられた。
ともあれ、森保監督の評価が急上昇したことで、日本人監督は海外の監督にかなわない、という思い込みはかなり拭い去られた。あの中国でさえ、サッカーに関しては日本人指導者を切望する空気が育ちつつある。
かつて、外国から呼ぶだけで自国から出て行くことはほぼ皆無だったスペインの指導者が、バルセロナの隆盛と自国のW杯優勝以降、全世界から引っ張りだこの状態になったように、あるいは、全世界の自動車メーカーがトヨタの製造工程の影響を受けたように、いずれは、日本人指導者も引く手あまたの時代がやってくるだろう。

森保監督が日本人指導者の評価とイメージを変えつつある中、Jリーグで脚光を浴びたのが町田ゼルビア、黒田剛監督だったというのも、なかなかに興味深い。
基本的には引退したプロ選手がなるもの、でしかなかったJリーグの監督は、少しずつではあるが多様性が見られるようにはなっていた。とはいえ、選手としての実績はほぼゼロ、プロでの指導経験もゼロという指導者が、J1昇格1年目のチームを優勝争いさせたインパクトはとてつもなく大きい。欧米史上主義者には受け入れがたいかもしれないが、100年を越える歴史を持つ若年層の、しかも一発勝負のトーナメント方式の大会で結果を出し続けてきた黒田監督の成功によって、日本のサッカーにはまた新たな鉱脈が存在していることが明らかになった。
勝敗をそれほど重視しない、いわゆる育成年代の指導者からトップレベルにまで駆け上がった人物なら、世界中にいくらでもいる。しかし、学校の命運という結構な重荷を背負いながら、勝ち続けることが要求される世界で結果を残してきた指導者というのは、全世界を見渡してもそうはいない。考えてみれば、高校サッカーの指導者ぐらい、敗北のリスクを排除することに長けた指導者はいなかったのだ。

黒田監督と町田のやり方には、賛否両論が渦巻いている。当然と言えば当然である。彼と彼のやり方は、かなりの部分ジャパン・オリジナルであり、多くの日本人指導者が抱いている「どこかのチームに対する憧れ」とは無縁の存在だからだ。ヨハン・クライフたちが世界を驚かせたオフサイド・トラップを、隣国ドイツのサッカー界は長く「卑怯な戦術」として認めなかった。通例から外れたやり方に対する反発は、洋の東西を問わない。
とはいえ、来年以降も町田が結果を残し続けるようなことがあれば、高校サッカーに源流を持つプロ指導者を抜擢しようという動きは、いよいよ本格化していくことが考えられる。全世界的に見ても極めて稀な“トーナメント・フットボールを主戦場としてきた指導者”が、一定数、プロの世界に入ってくれば、日本のサッカーはまた新しい局面を迎える。
まずは徹底的に受け入れ、ある時期を境に輸出へと転じていく。明治維新以降、この国がたどってきたのと極めて似通った道を、日本サッカー界は進んできた。その流れに、ついに指導者たちも乗った年──あとになって振り返ってみれば、そんな評価が下される24年だったかもしれない。
RECOMMENDED POSTS
この記事を見た方におすすめの記事