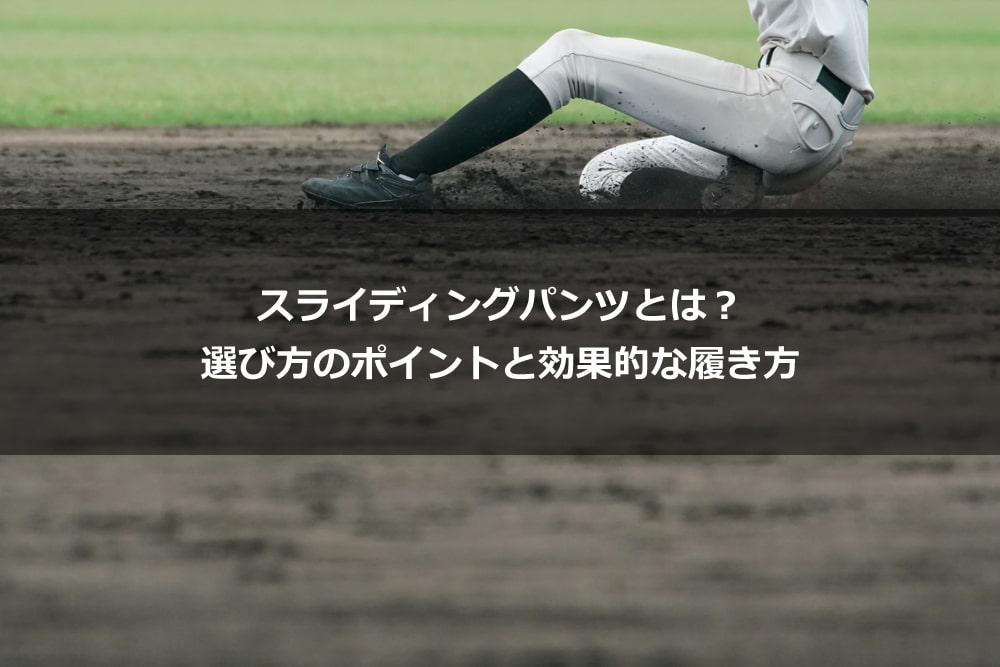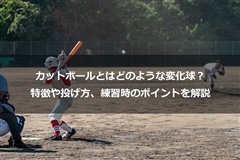【2023年日本野球界を総括】WBC優勝と大谷翔平の偉業、そして現役ドラフトの成果

個人的には、18年ぶりのセ・リーグ制覇、38年ぶりの日本一を果たした阪神こそが23年という年の象徴になるのだが、それはあくまでも内輪の話でしかないという自覚はある。オリックス・ファンからすれば「はあ?」ということになるだろうし、それ以外のチームのファンの方にとっても、愛するチームがペナントを制する可能性を失った時点で、シーズンはほぼほぼ終わっている。去年まで、自分がどんな気分で日本シリーズを眺めていたかを思い出せば、「阪神の躍進こそが23年の日本プロ野球界の象徴である」などと言い出す気にはとてもなれない。
では、野球ファンにとって、プロ野球を愛する人たちにとっての象徴とはなんだったのか。これはもう、言うまでもない。WBCの優勝であり、大谷翔平だろう。
WBCの優勝に関しては、ちょうど開催時期が3月、アメリカが大学バスケットボールの覇権争いに熱狂する「マーチ・マッドネス」の季節に当たっていたこともあり、日本人が思い描くほどには開催国が盛り上がっていなかった、という一面はある。つまり、日本人の熱狂が記録した熱量の絶対値ほどには、アメリカの失意は大きくなかった、ということ。実際、全米におけるWBC決勝の視聴者数は、アメリカとは関係のない国同士で行なわれたサッカーW杯の決勝のおよそ4分の1だった。
アメリカ代表の実力についても、必ずしも「最強」とは言えない部分があった。大谷と最後のアウトカウントを争ったトラウトを始めとして、打線はほぼベストに近かったが、故障に対する懸念を捨てきれなかったメジャーの球団が多かったことで、超一流の参加がほとんどなかった投手陣は明らかに見劣りがした。そんなことも、いま一つアメリカ国民の関心を勝ち取れなかった一因かもしれない。
ただ、そうしたマイナス面を考慮したとしても、3度目の栄誉を勝ち取った日本代表の戦いぶりは称賛に値した。とてつもなかった。日本中に野球の面白さ、奥深さ、物語性を広く伝えた功績は、現在というよりは将来、大きな意味を持ってくるだろう。たとえば、減少の一途を辿っていた野球人口が、この優勝を境に流れを変えた、といった形で。

そして何より、大谷翔平という存在が日本の未来を担う世代に与えた影響こそが、WBC優勝の持つ最大の意味だった。
日本は過去にも、WBCで優勝したことがあった。イチローは素晴らしかったし、松坂やダルビッシュの活躍も忘れられない。ただ、イチローが世界一のバッターか、ダルビッシュや松坂が世界最高のピッチャーかと言えば、そこは意見のわかれるところだろう。
王貞治よりはるかに多くのヒットを打った張本勲を、それでも史上最高の日本人打者と認識する人が必ずしも多数派ではないように、イチローには本塁打の少なさを問題視するアメリカの識者が存在した。ダルビッシュは、松坂は、アメリカのピッチャーにとって最高の栄誉であるサイ・ヤング賞を獲得していない。つまり、日本人にとっては世界最高のスーパースターではあっても、それはあくまで日本国内での話だった。
大谷の場合は、次元がまったく異なる。
日本人はもちろんのこと、野球を愛するアメリカ人にとっても、大谷翔平は別格である。比較の対象となるのは、もはや現役のスーパースターではなく、ベーブ・ルースという歴史的偉人であり、その比較競争すらも、はや終焉を迎えつつある。サッカーファンの方には怒られるかもしれないが、メッシでさえ、マラドーナでさえ、大谷ほど特別な存在ではなかったと個人的には思う。メッシにはクリ・ロナがいて、マラドーナにはペレがいた。つまり、まだ比較対象となる存在が実在していたからである。もはや、大谷と比較しうるのはペレであり、モハメド・アリであり、マイケル・ジョーダンであり、そんな伝説級の彼らでさえ、存在感や歴史上の意味において、大谷を圧倒しているとはいいがたい。
これまでの日本人は、勝つ日本代表を見たことはあっても、現在だけでなく、歴史上もその世界の頂点に君臨する日本人など見たことがなかった。日本人だけではない。世界ほとんどすべての国民が、世界の頂点を極める自国の選手など見たことがない。
だが、日本の少年たちは大谷翔平を見た。同じ国に生まれ、同じ国籍を持つ人間が、日本をはるかに超える存在となるところを目の当たりにした。長く世界大会における敗因の多くを「日本人であること」に見出してきた国民性は、今後、間違いなく変わる。世界の歴史がイエス・キリストの誕生以前と以後で区切られているように、日本人の意識そのものが大谷以前と以後で違ったものになる。
それが、2023という年だった。
ドジャースへの移籍に際して発生した金額が、あらゆるスポーツを含めて世界最高額だったという事実も、大谷翔平という選手がいかに桁外れの存在かということを物語っている。意地の悪い見方をする人の中からは、サラリーのほとんどを後払いにしたのは、カルフォルニア州の高い税率を嫌ったからだ、といった声も上がったようだが、それも大谷が無利子で後払いギャラを受け取ることにした、という事実の前では完全に説得力を失う。
これほど完璧で、いかなる悪意にも汚されないアスリートは、わたしの知る限り、ただのひとりとして存在しなかった。
というわけで、大谷翔平すべてで語り尽くせてしまいそうな今年1年だが、もう一つ、エポックメイキングな出来事があった。
現役ドラフトの成功である。
第一回の現役ドラフトが実施されたのは22年のことだから、厳密に言えば今年の話ではない。ただ、阪神の大竹が、中日の細川が大ブレークしたことで、この新しい制度の重要性は多くの人が知るところとなった。
長い間、日本のプロ野球は“選手ファースト”とは言い難い世界だったという印象がわたしにはある。偉いのは球団のトップで、選手は単なるコマ。それを象徴的に表したのが、かのプロ野球再編騒動の際にとあるグループのトップが発した「たかが選手が」という言葉である。
それでも、ドラフトの上位で入団した選手に関しては、まだ球団から優遇されている部分もあった。出場のチャンスは下位入団の選手より明らかに多く、また、許される低迷期の長さも、下位の選手とは違っていた。
現役ドラフトという新制度は、様々な理由で不遇を託つ選手たちに新たな機会を与えた。自分のところで使えない選手がヨソで活躍するようなことがあれば、チームとしてはマイナスでしかない。それでも、球団側は現役ドラフトの実施に賛同し、大竹や細川が新制度の有効性を見事に証明してみせた。新たに芽生えた“選手ファースト”の機運は、今後ますます高まっていくことだろう。
実を言えば、1年前のわたしはこの新制度にあまり大きな意味を見出せていなかった。組み合わせが変わればプレーが変わるサッカーと違い、野球の場合は140キロを投げるピッチャーはどこで投げても140キロであり、2割5分のバッターはどこへ行っても2割5分だと思っていたからである。
だが、他の競技に比べると、周囲との関係性とは独立した形で個人の能力を数値化しやすい野球でさえ、環境が変われば化ける選手がいることが、今年改めて明らかになった。近い将来、現役ドラフトはオフシーズンを彩る一大行事に成長していくだろうし、その規模は、2順目、3順目が必要となるぐらい拡大していくことも考えられる。
それにしても──。
ドジャースへの入団会見を見終わったいま、わたしの中にはある疑問が生じつつある。

大谷翔平とは、そもそも実在する人間なのだろうか。
何を馬鹿なことを、と思われる方がいらっしゃるかもしれない。ただ、大谷翔平という主語を、こう置き換えてもなお、あなたらわたしの思いを単なる戯言で片づけられるだろうか。
『160キロを超えるファストボールを投げ、ホームラン王を獲得し、しかもそれらを同時進行で行い、チームの勝利のためには目先の利益には目をつぶり、会見はあくまでも日本語で押し通し、それでもなおアメリカのメディアから批判を受けることなく、常に他者への気遣いと感謝を忘れず、かつ圧倒的な体躯と魅力的な風貌を持つ日本人男性』……が絶対に出現すると、10年前のあなたは思えただろうか。
わたしは、思えなかった人間である。
RECOMMENDED POSTS
この記事を見た方におすすめの記事