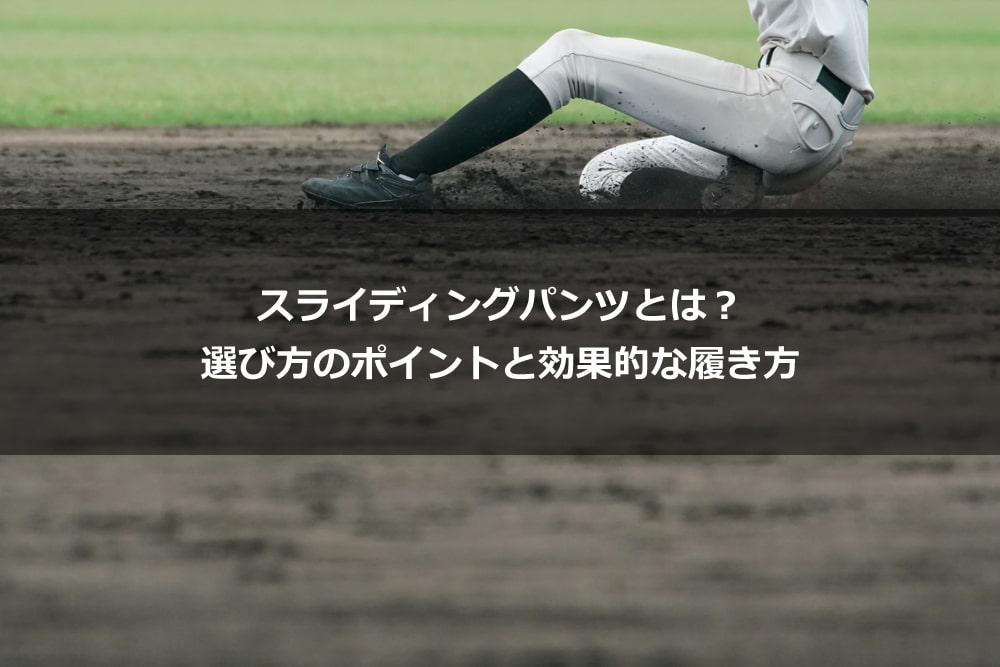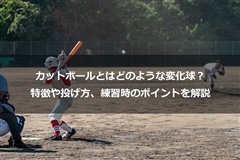新庄剛志(日本ハム・ファイターズ監督)の挑戦を、1年後どんな気分で振り返るのか

小学校3年生になる我が家の息子は、野球にまったく興味がない。
立派な阪神ファンになるべく、親から「虎」の字を与えられたというのに、物心つく前から甲子園やら神宮やら東京ドームやらハマスタやら、とにかく片っ端から阪神の試合に連れていかれたというのに、そもそも、野球という競技自体にまったく興味がない(ついでにいうと、サッカーにもまったく興味がない)。
だから、驚いた。
「あ、ビッボースだ!」
新庄剛志の顔がテレビに映った途端、ヤツは歓声をあげた。ちょっとネイティブ風に、というか日本ハムの監督就任記者会見で当の本人が「こう呼んでください」が希望した通り、日本語ではないアクセントをつけて“ビッボース”と言った。
自分に置き換えて考えてみる。何の興味もないオペラの世界で大事件が起きたとする。アフリカの小国でクーデターが起きたとする。果たして、わたしは事件当事者の名前を、クーデターを起こした軍人の名前を記憶するだろうか。
たぶん、しない。
わたしに限らず、人間の脳というものは基本的に自分が興味のあるものしか認知しないようにできている。最近、女性アイドル・グループの名前と顔がまるで頭の中に入ってこないのも、「若い女性」というカテゴリーがわたしの中で興味の対象外になってしまったから、だろう。
だが、新庄剛志と北海道日本ハム・ファイターズは、野球になんの興味もない小学生に、その存在を強烈に刻み込むことに成功した。我が家に限った話でいうと、彼らのメディア戦略は近年ちょっとないほどの大成功だったといってもいい。
実に、実に興味深い。というのも、いまから20年ほど前、新庄剛志はこんなことを言っているからである。少々長くなるが、紹介させてもらおう。
『ま、新聞はほとんどウソですからね。カギカッコがついていても僕のコメントじゃないケースがほとんどだから。マスコミ、関西、タイガースに僕は育ててもらったとは思ってるんですけど、そのマスコミがイヤでイヤで仕方がなかった。ウソ書かれたり、両親にも迷惑がかかるようなことがあったり、親戚にまで影響が及んだり、僕以外の人に迷惑をかけてしまうことが本当にイヤでした。そこまでして俺のことを記事にしようとする。俺はただグラウンドで野球をやればいいわけでしょ。結果が出れば、たとえばサヨナラヒットを打ったらそれがバンと一面に載るのはありがたいことだし、打てなかったらそれをしっかり見ててもらって、もっと練習しろとか、批判されるのはまったく問題ありません。野球のことであれば何を書かれても全然かまわないんです』(新庄剛志 shinjo5.net/二見書房)
20年前の新庄剛志、ニューヨーク・メッツでの1年目を終えて帰国し、対談のために恵比寿のホテルに姿を現した新庄剛志は、メディアに対する不信感や嫌悪感を隠さない男だった。メディアに対する不信感があったから、ホームページを立ち上げたのだ、とまで言った。
おそらく、版元の二見書房が考えたのは、ベストセラーになった中田英寿の『nakata.net』の便乗商法だったのだろう。ただ、本人の書き込んだ文章の量が、中田英寿に比べるとだいぶ少ない。そこで、誰かと対談をさせて、単行本に十分なボリュームを出そうということになった。対談相手として白羽の矢が立ったのが、どういうわけか、このわたしだった。
時間にしたら2時間なかったぐらいの対談は、そっくりそのまま活字となり、数週間後、単行本として店頭に並んだ。購買意欲を少しでも掻き立てるべく巻かれたオレンジ色の帯びには、対談を終えた直後のわたしの言葉がそのまま使われていた。
『メディアの“宇宙人”報道は全くのデタラメだった』
残念ながら、単行本の売れ行きはサッパリだった。ただ、わたし個人としては、変わり者の権化のように言われていた青年が、びっくりするほど野球に真摯な男だったこと、豪放磊落に見えて深く傷ついた部分があると知ることができて、忘れられない対談となった。
あれから20年が経った。

男子三日会わざれば、というが、21年の新庄剛志は、顔だけでなく、その考え方もずいぶんと変わっていた。いや、野球に対する真摯な姿勢に変わりはないのだろうが、少なくともメディアとの付き合い方、利用の仕方は180度といっていいぐらい、劇的な方向転換を遂げていた。
メジャーリーガー、ファイターズのスター、バリ島の自由な生活を経た新庄は、ただグラウンドでのプレーに没頭したがっていた頃の彼ではない。メディアを敵ではなく、情報とイメージを発信する手段と捉えるようになっている。
そして何より、日本の野球界を変えようとしている。
監督ではなく“ビッボース”と呼んでほしいという彼の言葉は、いまのところ、概ね好意的に受け止められている。それは、ほとんどの人が、この発言をちょっとしたジョークの一種として受け止めているから、かもしれない。
だが、笑いというオブラートにくるまれて発信されたこの要望は、ひょっとすると、野球界、日本のスポーツ界に向けた鋭い刃となるかもしれない。
監督という言葉は、本来、取り締まる者、指図する立場の人間を示す。取り締まられる側、指図される側との関係は、決して対等ではない。そして、長くこの言葉が使われてきてしまったからことが、日本のスポーツ界にパワハラがはびこり、また、その立場についた者が異様なほど責任を問われる一因になっているとわたしは思う。
ヘッドコーチ、ディレクターという単語に接して「絶対君主」をイメージする外国人はほとんどいないはずだが、日本のスポーツ界における「監督」には、そうした印象がいまだつきまとう。
そして、旧来のイメージ通りの監督像を期待する日本人は、依然として少なくない。
ビッグボスになるか、要望通りビッボースになるか、いずれにせよ、新庄剛志が結果を残し、この呼び名が一般的になれば、日本の野球界、スポーツ界は変わる。ほんの少しかもしれないが、確実に変わる。
そのために、変えるために、新庄剛志は道化にもなる覚悟を固めたようだ。かつて、絶望的に深いメディア不信を抱えていた青年がここまでの変化を遂げるには、相当な痛みや葛藤もあったはずだが、ともあれ、彼はやると決めた。
こちらの気持ちは千々に乱れる。
というのも、スポーツライターとしてのわたしは、新庄剛志がやろうとしていることを好意的に見ている。一方で阪神ファンとしてのわたしの中には、「アレをウチのチームでやられたらちょっとイヤかも」と感じている部分がある。つまり、旧来の監督というイメージに縛られている社会をシニカルに眺めているようで、他ならぬ自分自身がそこから抜け出せていないことが実感できてしまう。まるで、家庭内では完全な亭主関白なくせに、外面はリベラルぶっている議員センセになってしまった気分である。
新庄剛志、恐るべし。
いまだかつて、パ・リーグの新人監督がここまで世間から注目されたことはなかった。現役時代の実績では新庄を遥かに上回るレジェンドを新監督に据えた中日の話題は、完全にかき消されてしまった感がある。
果たしてこの現状を、1年後のわたしたちはどんな気分で振り返るのか。当然?単なるから騒ぎ?それとも、足りなかった?
いずれにせよ、来年の日本ハム・ファイターズは、球団史上もっとも多くの視線が注がれてシーズンを戦うことになる。それだけで、この挑戦的な人事は半分以上成功している。
ま、阪神ではできない人事だわな。
RECOMMENDED POSTS
この記事を見た方におすすめの記事