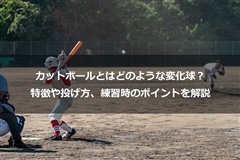小野塚勇人(劇団EXILE)│「あのときサッカーから逃げてしまったから、役者は絶対にやめない」【後編】

[
前編はこちら
]
劇団EXILEのメンバーとして活躍する小野塚勇人さんに、学生時代のサッカー経験について聞いた本インタビュー。後編では、憧れだった市立船橋高校での葛藤、その後役者になるまでの道のり、そして現在部活動に打ち込む学生たちへのメッセージをお届けする。
■高校に入って「自分はプロになれない」と思った
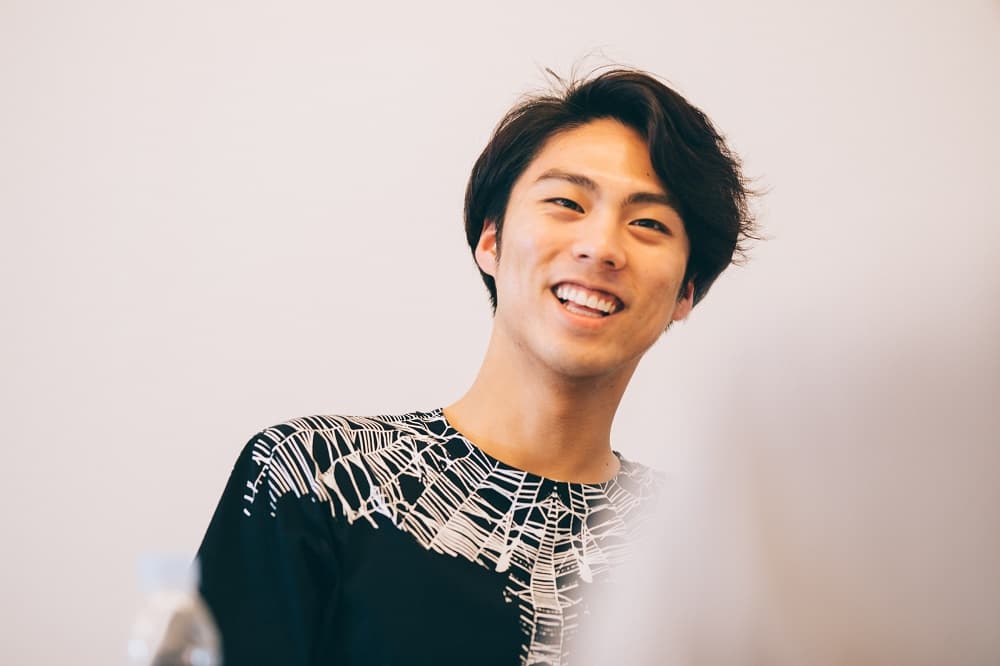
──憧れの市船サッカー部に入って、いかがでしたか?
レベルが段違いでした。僕は小学生のころからプロサッカー選手になりたいっていう“夢”を持っていて、15歳くらいのときには、なるって“決めてた”んですけど。高校に入って、「多分プロにはなれない」って。今、名古屋グランパスで活躍している和泉竜司選手とは高校で同期だったんですけど、彼を見た瞬間に「こういうやつがプロになるんだ」って思いました。しかも、僕は竜司と同じフォワードだったので、このままじゃ一生試合に出られない、と。それからサイドバックをやったりしたんですけど、まぁ走れないし、難しいし。練習も死ぬほどキツイし。高校になると戦術的なことも増えてきて、フォーメーションとかサインとかいろいろ決めたり覚えたりしていくうちに……何だかサッカーが“仕事っぽい”と思えてきちゃって。
──中学で純粋にボールを追いかけてきたからこそ、ギャップを感じてしまったのでしょうか。
もちろん中学生のころも考えてプレーするようにはしていたんですけど、やっぱり変化は大きかったですね。そこからまた努力を続けていたら、絶対にプロになれたとは思うんですけど。周りの実力だったり、サッカーを“やらなきゃいけないもの”と感じてしまったことだったり、いろいろ現実を見ちゃって。「サッカーは好きなんだけど、嫌い」みたいなモヤモヤがしばらく続きました。チームのみんなが本気でやっているからこそ、このまま僕みたいなやつがいたら失礼だなっていうのもあったし。そのうち、自分の中でサッカーへの熱がプツンとはじけちゃったんですよね。
──それまでの小野塚さんだったら“負けず嫌い”を原動力に立ち向かうことができそうですが、そうならなかったのはどうしてだと思いますか?
以前の僕だったら部活の時間以外にもめちゃくちゃ自主練してたと思うんですけど。それまでサッカー漬けでほとんど遊んでこなかった反動で、遊びが楽しくなっちゃったのもあるんですよね。そのタイミングでEXILEさんの曲を聴いたり、テレビで“オカザイル”を見たりして。友達とカラオケに行ったら「歌うまいね」って言われることも多くて、ちょっとずつ「EXILEになりたい」って思うようになりました。気持ちとしては、サッカーを始めたときの「褒められたい」っていうのと同じで、単純でしたね。それからはもう「EXILEのヴォーカルになろう」と決めて、1年生の夏の練習後にいきなり「俺、もう練習来ないから。EXILEになるから」って言ってやめたんです。
■久しぶりに反骨心のスイッチが入った

──ずっと努力を続けてきたサッカーをやめることに、葛藤などはありませんでしたか?
もちろん、悶々とする気持ちはありました。それまでサッカーしかやってこなかったから、「サッカーをやめる=自分の人生を否定する」ことになってしまう気がして。でも、もう本当に自分の中で音が聞こえるくらい、プツンと糸が切れちゃったんですよね。周りには、やっぱりすごく止められました。親も泣かせてしまったし、小学校のときのクラブチームのコーチが電話してきてくれたり。ヴィヴァイオ時代から僕のことを知ってる市船のコーチにも「何でやめるの?」って問いただされて。さすがにそのときは「EXILEになりたい」って言えなくて、「練習キツイし、試合にも出られないし、熱が冷めちゃって」みたいな超甘ったれたようなことを言ったんですけど。「そのままだと、お前の人生ずっと中途半端になるよ」って言われた瞬間、久しぶりに反骨心のスイッチが入ったんです。歌手になって、EXILEになって、「絶対に中途半端じゃない人生にしてみせる」って思いました。その後はバイトをしながらEXPG STUDIOに通って、歌手を目指すようになりました。
──チームメイトの反応はいかがでしたか?
きっと内心は「何で突然?」って感じだったと思います。でも、ありがたいことに同期のチームメイトたちは僕がやめてからも普通に接してくれたんですよね。部活をやめてからは正直学校にもいづらくなってしまって、高2から高3に変わるときに僕は転校しちゃったんですけど。でも、高3のときに最後の高校サッカー選手権をこっそり観にいって。気まずいなって思ってたら、応援席にいた当時のチームメイトが「勇人来いよ! 一緒に応援しよう!」って声をかけてくれたんです。それから毎試合観に行って、どんどん勝ち進んで。最終的に市船は全国制覇するんです。サッカーをやめてからの約2年間、一人で歌手を目指すなかでいろいろと道に迷いかけたこともあったんですけど、彼らが必死にサッカーしているのを見て、改めて背筋が伸びました。決勝の残り数分で同点に追いついたときは、鳥肌と涙がすごくて。あんなに声を出して泣いたのは人生であのときだけです。
──市船の優勝を目の当たりにしたのを機に、歌手の夢に向かう姿勢や考えで具体的に変化したことはありますか?
それまでは、何となく「25歳までに芽が出なかったら歌手をあきらめて働こう」って考えていたんですけど、その試合を見たときに「“今年でもう終わり”くらいの気持ちで追い込まないとだめだ」と思いました。それで決意したタイミングで劇団EXILEの舞台のオーディションがあって、選んでもらえて。その後の3ヶ月間の稽古がめちゃくちゃ厳しくて、夢の中でも稽古してたくらいなんですけど、市船が優勝した姿を見たあとだったので「決めたことだから」って頑張れました。それまで散々LDHのオーディションに落ちてきたうえでのチャンスだったし、もともと目指していた歌手の道とは違ったけど、そのまま役者を目指してみたいとも思えていたし。「これでまた逃げたら市船やめたときと何も変わらない」と思って、3ヶ月間必死で稽古についていきました。
■形は変わっても、夢が叶うことがある

──現在も、サッカーの経験が活きていると感じることはありますか?
純粋な努力というか、ひたむきさ、がむしゃらさはサッカーで培われたものだと感じています。あとは、LDHでは『EXILE CUP』というフットサルの大会をやっていて。僕も全国の大会をまわらせてもらうこともあるんです。そこで小学生たちに「サッカーうま!」って言ってもらえたり。ほかにも、役者になったからこそ、元日本代表監督の岡田武史さんや、ラモス瑠偉さんにお会いできる機会があったり、CMでサッカー選手の役をやらせていただいたり。そのCMが、日本代表戦のハーフタイムに国立競技場のスクリーンに映ったときは本当に鳥肌が立ちました。昔は、自分がプレーヤーとして国立競技場のピッチに立つことが夢でもあったので、別の形で少し叶ったというか。サッカーをやめるときには親も泣かせちゃいましたけど、CMが流れたときには喜んでくれましたし。サッカーを諦めた人間が、役者として別の角度でサッカーに関われることもあって、すごく不思議な感覚です。
──高校生のときには「サッカー以外の人生を貫き通してみせる」と思っていた小野塚さんが、今となっては役者としてサッカーに関わることがあることに、何だか縁を感じますね。
本当に縁は感じますね。「サッカー選手になりたい」「仮面ライダーになりたい」「市船に入りたい」「EXILEになりたい」と、これまでに抱いてきた夢が、いろいろな縁のおかげで叶うことがあって。想像とは違った形で叶うこともあるけれど、やっぱり嬉しいですね。
──最後に、小野塚さんが高校時代のご自身に、今だからこそ何か声をかけるとしたら、何を伝えたいですか?
まずは、EXILEにはなれなかったけど劇団EXILEに入ったよ、と(笑)。
あとは何だろうな……。当時の僕自身にというよりも、今部活を頑張っている高校生に対して伝えたいのは、「ただやめるくらいだったら、続けたほうがいい」ということ。多分、僕と同じようにキツくなってやめたいっていう人、全国にたくさんいると思うんですよ。でも、高校3年間部活を続けた人とそうじゃない人では、めちゃくちゃ差があると僕自身は感じたんですよね。3年間やり通した人には、やっぱり“芯”がある人が多い。ただ、それに代わる情熱を見つけられたのだとしたら、スパッとやめてもいいと思います。きちんと考えて“切る”判断をできる人は、それはそれで強い人だと思うので。
とは言っても……難しいですよね。やっぱりつらかったら続けられなくなってしまう子もいると思う。実際、自分も逃げた人間だから、気持ちはすごくわかります。だから、結局は前向きになることが大切ですね。もし逃げてしまったとしても、そこに負い目を感じるんじゃなくて、どうやったら自分の人生が豊かになるかなって、明るいほうに考えて。ときには、弱い自分を受け入れることも必要だと思う。
僕は、「あのとき逃げてしまったからこそ、今の自分がある」と自信を持って言えるようにしたいんです。「サッカーをやり通さなくて本当に後悔していないか」と言われたら、まだ「あのまま続けていたら違う人生もあったのかな」と考えちゃうことはありますけど。だからこそ、役者は絶対にやめたくないし、これからもっと突き詰めていきたいです。
■プロフィール

小野塚勇人
俳優。1993年生まれ。千葉県出身。劇団EXILEメンバー。2012年劇団EXILEに加入。舞台、映画、TVドラマ、CMなどで幅広く活躍中。
映画「東京ワイン会ピープル」が10月4日公開予定。
https://twitter.com/Hayato_Onozuka
RECOMMENDED POSTS
この記事を見た方におすすめの記事