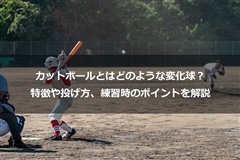堀口恭司が、山本“KID”徳郁から受け継いだ大切なこと

2年間ほど、バルセロナに留学していたことがある。
週末はカンプ・ノウかサリアに試合を観に行く。「サリア?」と思われた方のために説明しておくと、中村俊輔が移籍したころには更地にされてしまっていた、RCDエスパニョールの本拠地のこと。82年のスペイン・ワールドカップでは、ブラジル対イタリアの伝説的な一戦が行なわれたスタジアムでもある。
オンボロで、トイレは悪夢のようで、でも当時の日本人の感覚としては信じられないほどにピッチとスタンドが近かったこのスタジアムが、わたしは大好きだった。すべての面でバルサに劣っていることを自覚しながら、「♪バルセ~ロ~ナ~、ソ~ロ・ブランキアスール、ソ~ロ・ブランキアスール」と『イエロー・サブマリン』のメロディに乗っけて歌うサポーターも好きだった。
ソロ=オンリー。ブランキアスール=ホワイト&ブルー。バルセロナにあるサッカーチームは青と白だけ、エスパニョールだけという、傍からみればジョークにもならないフレーズを、彼らは大まじめに叫んでいた。どんなに負けても六甲颪をうたい続けてきた人間としては、彼らを、チームを、好きにならずにいられなかった。
ただし、それはあくまでもこちら側の話。
あちら側、つまりエスパニョールのサポーターの中には、スペインの中でも屈指の極悪集団と見なされていた輩たちがいた。ネオナチを気取り、UEFAカップでオランダのチームが乗り込んで来た際など、ご丁寧にナチス式の敬礼で選手の入場を迎え、オランダ・メディアを激怒させたことがある(ただし、公式なお咎めはなにもなし。のどかな時代だった)。
そんな彼らにとって、日本人、というか東洋人は差別と嘲笑の対象だった。幸運にもわたしは被害にあったことはないが、日本人の知り合いが取り囲まれ、ツバを吐かれたり汚物を投げつけられたり、という話はよく聞いた。無教養な彼らは、かつて日本がヒトラーやムッソリーニと手を組んでいたことなど、もちろん知らない。
そういった行為をする人に共通したのが、スキンヘッドだった。ただのスキンヘッドではなく、たっぷりと全身にモンモンを彫り込んだスキンヘッドだった。
なので、ちょっと信じられなかった。日本に帰国してしばらくたち、格闘技も取材するようになったころ、酒の席で日本の格闘家が言っていたことが。
「入れ墨を入れてるような選手って、基本的に気の弱い選手が多いかな」
いや、あの、それにはちょっと賛同しかねるっていうか、ヨーロッパのサッカー場にいるタトゥー入りのスキンヘッダーって、気が弱そうどころか、めちゃくちゃヤバそうな雰囲気がビンビンだったんですけど。
「でもさ、たとえばヒョードル。強いお兄ちゃんは綺麗な身体だけど、弟は入れ墨だらけでしょ」
う、あ、まあ、それはそうかも。
「本当に自分に自信のあるヤツは、別にタトゥーとかで相手を威嚇する必要がないわけよ。入れりゃ強くなるっていうなら、俺だって入れるけどね」
わたしはいまでも、「タトゥー=気の弱いヤツ説」は、サッカー界には必ずしも当てはまらないと思っている。メッシはクリロナより気が弱いか? う~ん、なんとも言い難い。ただ、タトゥーの入った格闘家をみると、サリアで遭遇したときに感じた禍々しさではなく、ちょっとした親しみの情さえ抱くようにはなった。不安を隠して頑張ってるんだな、と──。
同時に、綺麗な身体の格闘家をみると、無条件で神々しさを覚えるようになった。
いま、わたしが一番神々しさを覚えるのは、堀口恭司である。
ボクシングの世界王者がタトゥー問題で騒がれるご時世とはいえ、こと日本に関する限り、まだまだタトゥーを入れたアスリートは少数派と言っていい。RIZINのリングにあがっている日本人ファイターを見ても、それは明らかである。
ではなぜ、タトゥーを入れていない他の日本人ファイターではなく、堀口にのみ特別なものを感じるのか。
山本“KID”徳郁の内弟子だったから、である。
幼少時から空手をやってきた堀口は、群馬県の高校を卒業すると同時に、山本が主宰していたジム“KRAZY BEE”に入門した。堀口にとっての山本は、師匠であると同時に、憧れの人でもあったに違いない。
そういう場合、たいてい、弟子は師の人となりをなぞる。

実はこのコラムの取材で、一度だけ、“KRAZY BEE”にお邪魔したことがある。山本“KID”のお姉さん、山本美憂さんのインタビューだった。
ジムのスタッフが素晴らしく協力的だったこともあって、取材はなんのトラブルもなく終わった。施設の充実ぶりも印象に残った。
だが、それ以上に、というか強烈に記憶に残っているのが、ジム生たちの“タトゥー率”の高さだった。皆礼儀正しく、こちらが不快な思いをすることはまったくなかったのだが、正直、あまりの多さに面食らったことを覚えている。
そらそうだ。憧れの人が入れているんだから。
師匠が入れている。弟子たちも入れている。もしわたしがジムの一員であれば、「じゃ、俺も」とばかりに入れていたことだろう。憧れ+同調圧力。会社を辞めるや否やヒゲを生やし、髪を茶髪に染め、左耳にピアスを開けたわたしは、「それがフリーランスだから」と思い込んでいたわたしは、たぶん、あっさりと周囲に染まる。
堀口恭司は、染まらなかった。
高校を卒業するや否やジムの門戸を叩くほどに憧れていながら、完全に同化することはせず、彼は自分のスタイルを貫いた。簡単なことではなかったはず、とわたしは思う。
そして、「みんながやっているから」で思考停止することなく、自分の意志を持っていたからこそ、彼は世界トップクラスのファイターたりえたのではなかったか。
圧倒的不利を承知で那須川天心とキック・ルールで戦ってみたり、誰もが見たいけれども彼の立場になれば勝って得るものがあまりないように思えた朝倉海と一戦を受けてみたり。時に手痛い敗北を喫することがあっても、そのたびに彼は立ち上がる。
タトゥーは引き継がなかったけれど、もっと大切なものはきちんと師匠から受け継いでいるのだな、とわたしは思う。