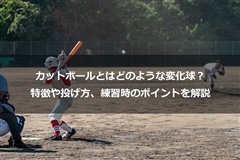田臥勇太が居たから、日本にバスケットボールが根付くと信じることができた

スポーツライターになりたい、という若者を集めて私塾のようなものをやっていた20年ほど前(わたし自身30代半ばの若造だったが)、よく聞かれたことがある。
「次はどんなスポーツが来ると思いますか?」
彼らが求めていたのは、つまり、いまはあんまり脚光を浴びていないけれど、いずれスポーツライターとしての需要が大幅に高まりそうなスポーツはなにか、という答だった。
わたしの答は決まっていた。 「ゴルフか、バスケット。特に、バスケ」
当然,彼らは理由を聞いてくるので、わたしはちょっと自慢げかつ自信タップリに答える。
「マンガ」
わたしが大学を卒業した88年は、バブル景気のまっ最中だった。就職は「するもの」ではなく「してやるもの」みたいに考えている学生が珍しくない時代で、内定を出した学生に逃げられないよう、企業がいわゆる「囲い込み」をすることも多かった。学生からすれば、ただ飯、ただ旅行をさせてもらえる美味しい機会だったが、それぐらい、企業側は人材確保に必死だったのだ。
そんな時代に、まだプロもなかったサッカーの専門誌に就職しようとしたわたしは、周囲からすれば完全な異端児扱いだった。なんというか、学生時代に演劇にハマリ、食えるか食えないかを度外視してその世界で生きていこうと決意した若者が向けられるような、同情と驚嘆と憐憫が入り交じった視線に出くわすことがよくあった。
だが、わたしとしては、演劇の世界に飛び込むよりはもう少し、ほんの少し、勝算はあるつもりだった。近い将来、サッカーの人気が大幅に高まり、サッカーで食べていくこともできるようになる、なってほしい、お願いだからなって、な感じだった。
その理由が、マンガだった。
日本リーグには閑古鳥が鳴きまくり、メキシコW杯を観に行ったわたしがサッカー部の仲間からも変人扱いされた当時の日本サッカー界ではあったが、サッカーをやる子供たちの数は劇的に増えていた。
『キャプテン翼』の影響だった。
相変わらず人気はないけれど、底辺は広がり、競技の魅力を広めるマンガの存在があり、かつ、このジャンルの代表作と言えるノンフィクション作品がないサッカーならば、大手出版社や新聞社からは洟もひっかけられなかった人間でも、何とか勝負できるかも──大学4年生のわたしは、本気でそう信じていたというか、信じたがっていた。
幸運なことに、わたしがサッカー専門誌を出している出版社に拾ってもらった5年後、日本にはついにプロのサッカー・リーグが発足し、マイナーなだけでなく、ある雑誌から「退屈な競技ナンバーワン」と揶揄されたこともあるサッカーは、人気スポーツの一つにのし上がった。サッカーをメインとするフリーのスポーツライターとなったわたしは、ハンバーグを注文するのが精一杯だったファミレスで、値段を気にせずステーキを注文できるようになった。
私塾を始めたのは、その数年後だった。そして、当時のわたしの目には、『あした天気になあれ』や『風の大地』のあるゴルフ、そして『スラムダンク』という超人気作のあるバスケットが素晴らしく魅力的に映った。
ではなぜ、ゴルフよりバスケの方により可能性を感じたのか。
田臥勇太がいたから、だった。
横浜市立大道中から秋田県の能代工に進み、史上初となる高校タイトル9冠を獲得した田臥は、00年、ハワイにあるブリガムヤング大学ハワイ校へ留学した。
ちょっと前のサッカー同様、国内リーグは活況を呈しているとは言い難く、代表チームは世界のトップからは縁遠いレベルにあったバスケットだが、底辺の競技人口は多く、そこに、日本人初のNBAプレーヤーとなるのも夢ではない、とされる田臥が出現した。
サッカーにおけるカズと同じ役割を果たすのでは、とわたしは思った。それが、ゴルフよりバスケに魅力を感じた最大の理由だった。
本人からすれば到底「成功した」というレベルではないのだろうが、それでも、彼は本当に日本人初のNBAプレーヤーとなった。運営面でのゴタゴタはあったものの、バスケットボールのプロ・リーグは着実に地域に浸透し、たとえば沖縄などでは県で最もチケットが入手しにくいスポーツ・イベントと言われるまでになった。
そして、田臥が初めて足を踏み入れたNBAという最高峰の舞台は、いまや複数の日本人が活躍するようになった。「日本人だから無理」だった日本人の思い込みを、「日本人でもできる」に変えた田臥の功績は、言葉にできないぐらいに大きい。
どうでもいいことだが、おそらくは日本バスケ界の伝説として長く語り継がれていくであろう田臥は、わたしの中学校の後輩でもある。
横浜市でもっとも校庭の狭い中学でもあった大道中は、わたしが入学した最初の夏、バレーボール部が全国大会3位になったことをきっかけにして、バレーコートを拡張しようということになった。
弱小だったサッカー部が生贄になった。まるでやる気のなかった顧問の先生はあっさりと廃部に同意し、サッカー部が明け渡したスペースはバレー部と、県内でメキメキと力を発揮しつつあったバスケ部に振り分けられた。
理不尽な理由で廃部に追い込まれたことで、単にやらされていただけだったわたしのサッカー熱は突如として暴騰した。より充実した環境を手にしたバスケ部はいよいよ県内の強豪としての地位を確立し、そこに小学校時代から注目されてきた田臥がやってきた。
つまり、学生の時にメキシコへ行くことを決心させ、サッカーに関わる仕事をしていこうと決めたのも、田臥が大道中にやってきたのも、元を辿ればバレー部の躍進とサッカー部顧問の無気力に原因があったということになる。
「というわけで、田臥勇太とは浅からぬ因縁があるのだよ」
飲み会のたびにわたしが口にしてきたこの自慢を、数年前、直接本人に伝える機会があった。雑誌『Number』での「その後のスラムダンク」という企画での取材だった。
後輩は大笑いして言った。
「ありがとうございます、センパイ。じゃ、今度メシ驕ってください」